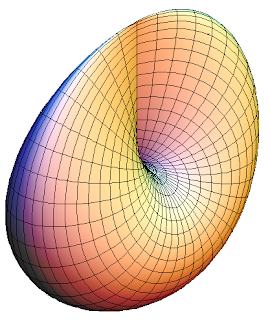Interview de Jacques Lacan sur France Culture, juillet 1973
– à l'occasion du 28ème Congrès de l’IPA à Paris
FRANCE-CULTURE –
Docteur Lacan, en ce moment se tient à Paris le 28e Congrès International de
Psychanalyse. Vous n’êtes pas invité, vous n’en êtes pas.
LACAN – Que je
n’y sois pas invité ne veut pas dire que j’en sois absent. Pour autant que mon
sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m’y
met en situation privilégiée.
Ceci, en raison
du poids de mon enseignement, qui, avec retard sans doute, fait son chemin
parmi ceux-là mêmes qui m’excluent, car ils ne se privent pas d’y faire le plus
large emprunt.
L’enseignement
que je reçois de mon expérience, à savoir de l’analyse qui est une expérience
très suffisamment définie et limitée pour permettre qu’on la qualifie comme
telle.
Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré, ce qui
n’exclut pas que dans certaines conditions ce soit difficile de s’en sortir.
C’est pourquoi il est préférable que l’analyste qui, heureusement, n’y a
pas toute la part d’action, sache ce qu’il fait.
Savoir ce qu’il fait, ça veut dire savoir dans quel discours il est pris,
car c’est cela qui conditionne l’ordre de faire dont il est capable.
J’ai prononcé le mot « discours ». C’est une notion très élaborée.
Je l’ai élaborée sans doute à partir de cette expérience.
Il faut quand
même bien admettre que vingt ans où je me suis laissé enseigner par
l’expérience et où je me suis efforcé d’en extraire quelque chose, vingt ans,
ça permet d’élaborer... Ce qui ne veut absolument pas dire que, de cela, je soutire
une conception du monde.
Ce que je définis,
c’est ce qui peut se dire à partir de cette expérience, de cette expérience
nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c’est-à-dire de ce
qui constitue un mode de lien social.
F.C. – Vous
n’êtes pourtant pas le seul à vous être intéressé au discours. Est-ce que ce
n’est pas le fait du psychanalyste qui se penche plus particulièrement
justement sur le formalisme de l’analyse ?
LACAN – On peut
poser la question en ces termes. C’est vraiment un point de départ. C’est
d’ailleurs de là qu’est parti ce qui se trouve situé comme mon enseignement.
L’analyste
reconnaît-il ou pas ceci que j’enseigne – que l’inconscient est structuré comme un langage ?
C’est la formule clef, n’est-ce pas, par laquelle j’ai cru devoir
introduire la question.
La question est celle-ci : ce que Freud a découvert et qu’il a épinglé,
comme il a pu, du terme d’inconscient, ça ne peut, en aucun cas, rejoindre
d’aucune façon ce que lui-même se trouve avoir mis en avant – les tendances de vie, par exemple, ou les
pulsions de mort –, ça
ne peut, en aucun cas, y être identifié.
Ce que Freud a découvert, c’est ceci : c’est que l’être parlant ne sait pas
les pensées – il a
employé ce terme –, les
pensées même qui le guident. Il insiste sur ce que ce sont des pensées. Et
quand on le lit, on s’aperçoit que ces pensées, comme toutes les autres, se
caractérisent par ceci : qu’il n’y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la
parole, qui n’appartienne au champ du langage.
La façon dont Freud opère, part de la forme articulée que son sujet donne à
des éléments comme le rêve, le lapsus, le mot d’esprit. S’il met en avant ces
éléments-là, il faut lire ces ouvrages de départ qui sont La Science des Rêves, la
Psychopathologie de la vie quotidienne ou justement ce qu’il a écrit sur Le Mot d’esprit, pour s’apercevoir que...
il n’y a pas un seul de ces éléments qu’il ne prenne comme articulé par le sujet.
Et c’est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation.
La nouvelle forme
qu’il lui substitue par l’interprétation, est – je dirai – de l’ordre de la traduction.
Et la traduction, chacun sait ce que c’est – que la traduction, on commence à s’y
intéresser peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu’importe –, c’est toujours une réduction. Et il y a
toujours une perte dans la traduction.
Et bien, ce dont
il s’agit, c’est en effet qu’une perte – on touche, n’est-ce pas ? – que cette perte, c’est le réel lui-même de l’inconscient, le réel même
tout court.
Le réel pour
l’être parlant, c’est qu’il se perd quelque part, et où ? – c’est là que Freud a mis l’accent –, il se perd dans le rapport sexuel.
Il est absolument
fabuleux que personne n’ait articulé ça avant Freud, alors que c’est la vie
même des êtres parlants. Qu’on se perde dans le rapport sexuel, c’est évident,
c’est massif, c’est là depuis toujours, et après tout, jusqu’à un certain point,
on pourrait dire que ça ne fait que continuer.
Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c’est dans la mesure où dans
la sexualité l’être parlant bafouille.
Pendant longtemps,
ça n’a pas empêché qu’on aille imaginer la connaissance sur le modèle de ce
rapport en tant qu’il est rêvé. Et, comme je viens de le dire, « rêver »
veut dire là, « bafouiller », mais « bafouiller en mots ».
Un professeur qui
a écrit en marge de mon enseignement, il a cru faire une découverte en disant
que le rêve ne pense pas. C’est vrai, il ne pense pas comme un professeur.
Trompe-t-il ou se
trompe-t-il, le rêve ? Le professeur ne veut pas poser la question au rêve pour
que le rêve ne la renvoie pas au professeur.
C’est ce qui
éclaire maintenant que, pendant la plus grande partie de l’histoire, l’être
parlant s’est cru en droit de rêver, et qu’il n’a pas su qu’il se laissait
porter par le rêve dans son droit fil.
L’ennuyeux est
qu’il en reste des choses totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence,
et la psychologie au premier plan.
Que chacun fasse
référence à sa vie parmis ceux qui m’écoutent. Est-ce qu’il a ou non le
sentiment qu’il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même,
et que c’est ça qui est le plus lui.
Qu’est-ce que c’est
que ce quelque chose qui se répète ? Un certain mode du jouir. Le jouir de
l’être parlant que vous êtes tous – vous qui m’écoutez – s’articule.
C’est même pour ça qu’il va au stéréotype, mais un stéréotype qui est bien le
stéréotype de chacun.
Il y a quelque chose qui témoigne d’un manque vraiment essentiel. Même les
philosophes – il
est vrai que c’est sur le tard avec Spinoza – étaient arrivés à ça : que l’essence
de l’homme est le désir.
Il est vrai
qu’ils ne mesuraient pas bien à quel manque le désir répond.
À quelque chose – il faut bien le dire – de fou.
À quoi, pendant longtemps on a substitué la perfection attribuée à l’Être
suprême. Cet accent sur l’être, c’est ce qu’il y a de fou là-dedans.
L’être se mesure
au manque propre à la norme.
Il y a des normes
sociales faute de toute norme sexuelle, voilà ce que dit Freud.
La façon de
saisir l’ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise
que là, pour meubler, on se rue avec toutes sortes de notations qui se
prétendent scientifiques, et on croit que ça éclaire la question.
C’est très
remarquable, ce double jeu de la publication analytique entre ce que peuvent
chez les animaux détecter les biologistes et d’autre part, ceci qui est tout à
fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal
sur sa vie sexuelle.
Les deux termes n’ont
aucun rapport : d’un côté c’est l’inconscient, de l’autre c’est une approche
scientifiquement valable, celui de la biologie.
Mais ce que nous
donne l’analyse, c’est que la question est personnelle pour chacun des êtres
parlants qu’on ferait mieux de dire des êtres parlés, ce qui montre bien que
c’est dans le langage que se joue l’affaire pour chacun.
Bien sûr que, comme on me le fait remarquer, il y a des affects. Mais c’est
du discours qui l’habite que procède l’appréciation juste de chaque affect
majeur chez chacun. Et ceci d’ailleurs se démontre très bien du progrès obtenu
dans le champ analytique sur un affect aussi important que l’angoisse.
Bon, disons
quelque chose de plus. L’analyse n’est pas une science. C’est un discours sans
lequel le discours dit de la science n’est pas tenable par l’être qui y a
accédé depuis pas plus de trois siècles.
D’ailleurs, le
discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu’on appelle
l’humanité.
L’analyse, c’est
le poumon artificiel grâce à quoi on essaie d’assurer ce qu’il faut trouver de
jouissance dans le parler pour que l’histoire continue.
On ne s’en est
pas encore aperçu, et c’est heureux, parce que dans l’état d’insuffisance et de
confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main
dessus. Pauvres analystes ! Ce qui leur aurait ôté toute chance d’être ce
qu’ils doivent être : compensatoires.
En fait, c’est un
pari, c’est aussi un défi que j’ai soutenu. Je le laisse livré aux plus
extrêmes aléas.
Mais, dans tout
ce que j’ai pu dire, quelques formules heureuses, peut-être, surnageront.
Tout est livré
dans l’être humain à la fortune.
F.C. – Vous avez fondé une école. Vous avez des élèves dont beaucoup d’ailleurs vous ont quitté,
quelques uns pour fonder plus récemment ledit Quatrième Groupe. Vous êtes
quelqu’un d’écouté passionnément, de controversé passionnément, de suivi. Selon
vous, quels sont vos continuateurs ?
LACAN – J’ai depuis quelques temps le bonheur de m’apercevoir que quelques-uns
de ceux qui sont restés autour de moi, non seulement ont su entendre ce que
j’ai appelé tout à l’heure quelques formules plus ou moins heureuses, mais
d’ores et déjà, savent leur donner plus qu’un écho : une suite. C’est
certainement bientôt qu’on s’apercevra comment mon enseignement peut être
repris ou continué.
F.C. – Est-ce que
vous recevez en ce moment justement du Congrès la visite de congressistes ?
LACAN – Oui, j’en
ai reçu bien sûr quelques-uns, comme c’est l’usage quand je suis à Paris.
F.C. – La
psychanalyse est devenue ces dernières années en France ce que nous appelons un
fait de culture. Je sais que vous contestez le terme.
LACAN – Oui, je conteste le terme, dans toute la mesure où celui de nature
auquel il s’oppose me paraît tout aussi contestable. Ce qu’on appelle un fait
de culture, c’est en somme un fait commercial.
Pourquoi dire que l’analyse, ça se vend bien ? Je parle de publications. Ça n’a absolument rien à faire avec
l’analyse. On peut entasser autant qu’on voudra de ces colonnes, de ces piles,
de ces entassements de productions diversement littéraires. C’est ailleurs que
se fait le travail – c’est
dans la pratique analytique, pour avancer là un terme que je regrette de ne pas
avoir avancé plus tôt, parce qu'il est là tout à fait essentiel.
Ce que j’essaie de former à la lumière d’une expérience suivie dans le
quotidien, c’est une École, celle que j’ai intitulée de freudienne comme telle.
C’est une École
pour autant qu’elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément
différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique.