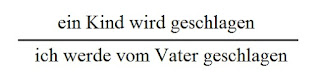1975年4月8日のセミネールで,Lacan は,数日前に Heidegger を訪ねてきたことについて語っている:「この復活祭休暇の間に,わたしは,Heidegger にちょっと会ってきた.我々がふたりともこの世からいなくなる前にちょっと挨拶をしてきたというわけだ.わたしは,彼のことが好きだ.彼は,まだとても元気だ」.
この訪問の際に Lacan に同行していた Catherine Millot は,彼女の著書
« La vie avec Lacan » (pp.87-90) のなかで次のように証言している:
その後しばらくして,わたしは,Lacan が Freiburg im Breisgau に
Heidegger を訪ねるのに同行した.Heidegger が脳卒中にみまわれたのを知って,Lacan は,彼自身の表現によると,「Heidegger が死ぬ前にもう一度会っておきたい」と思ったのだ.[訳注:実際,Heidegger は,この約一年後,1976年5月26日に死去した.]
Lacan は,Heidegger とは昔から知り合いだった.最初は,1950年代の始めに,[Heidegger をフランス語に翻訳した]Jean Beaufret とともに訪問している.ちなみに,Jean Beaufret は
Lacan に分析を受けていた.Lacan は,« Logos » と題された Heidegger のテクストをフランス語に翻訳している.その翻訳は,1956年に[Société
française de psychanalyse の学会誌] La Psychanalyse に発表された.1955年,Heidegger は,Cerisy-la-Salle
で行われた或る学会に Beaufret
と Maurice de Gandillac とによって招かれた.その帰途,Heidegger 夫妻は,Guitrancourt の Lacan の別荘に立ち寄り,数日間滞在した.Lacan は,夫妻のために,その地域を車で案内して回った
‒ いつものように,猛スピードで運転して.Heidegger 夫人が叫び声を上げるのを,彼は無視した.
我々は,まず飛行機で Basel へ行き,かの地のとても美しい美術館を訪れた.次いで,車を借りて,Heidegger 夫妻が我々を待つ Freiburg へおもむいた.
Heidegger 夫妻は,住宅街の比較的新しい家に住んでいた.それは,わたしが哲学者
Heidegger に結びつけていた森の山小屋のイメージには似ても似つかなかった.我々が中に入るや,Heidegger 夫人は,訪問者用のスリッパをはくよう我々に権威的に命令した.わたしは,Jura 県の出身なので,雪の季節,山岳地方ではそのような室内履きがごく普通に用いられていることを知っていた.北欧諸国では家に入るとき靴を脱ぐことも,わたしは知っていた.しかし,そのときはもう 4月だった.我々は外界の汚れを持ち込む者と見なされているのだ,とわたしは感じた.Freud は,無意識にとっては「外」は「異」 ‒ すなわち,敵,および,一般的に言って,憎むべきもの
‒ と同義である,と教えている.わたしは,一方では侵入者と見なされた不快感を感ずるとともに,他方では,スリッパと形而上学との思いがけぬコントラストが惹き起こした笑いをこらえていた.
我々は,応接間に通された.Heidegger は,長椅子に横たわっていた.Lacan は,Heidegger のかたわらに座るや,セミネールで展開中のボロメオ結びを用いた最新の理論的前進を伝えようとした.話を図解するために,Lacan は,四つ折りの紙をポケットから取り出し,そこに一連のボロメオ結びを描いて,Heidegger に見せた.後者は,その間ずっと,一言も発さず,目を閉じたままだった.この態度は,関心の欠如の表現なのか,それとも,認知能力が弱っているせいにすべきなのだろうか,とわたしは自問した.あきらめることを知らない
Lacan は,頑固に説明し続けた.この事態が永遠に続くのかと思われたとき,幸運にも,Heidegger 夫人が現れて,「会見」を終わらせた.「夫を疲れさせないために」予め定められていた時間が過ぎたのだ.我々は,スリッパをはいた足で出口に向かった.そのまま厄介払いというわけではなく,後ほど近所のレストランで一緒に食事をするよう招かれた.
スリッパのことがひどくしゃくにさわっていたわたしは,外に出るや,Lacan に質問した : Heidegger 夫人は Nazi だったのか,と.「勿論さ」と
Lacan は答えた.当時は,Heidegger と Nazismus との関係はさして問題にされていなかった.Victor Farias の本は,まだ出ていなかった.
食事の間,Heidegger の口数はもう少し多かったが,会話はほとんどはずまなかった.Lacan は,ドイツ語を読めるものの,話すことはできず,Heidegger 夫妻もフランス語はできなかった.別れ際,Heidegger は,葉書大の自分の写真をわたしにくれた.その裏面に彼はこう書いた:「Freiburg 訪問の記念に,1975年4月2日」.わたしの名前は書かれなかった.頼まれてもいないのに彼がファンのためにサインすることに,わたしはちょっとびっくりした.しかし,わたしはその写真をうやうやしく取っておいた.わたしの面接室の本棚にその写真を見かけた患者のひとりは,それはわたしの祖父なのか,と尋ねた.
Dans son
séminaire du 8 avril 1975, Lacan parle d’une visite récente qu’il a rendue à
Heidegger : « J’ai été faire une petite visite pendant ces vacances [
de Pâques ] ‒
histoire de lui faire un petit signe avant que nous nous dissolvions tous deux ‒ au nommé Heidegger. Je l’aime beaucoup.
Il est encore très vaillant ».
Catherine Millot
qui a accompagné Lacan lors de cette visite-là, en témoigne dans son livre
« La vie avec Lacan » (pp.87-90) :
Quelque temps
plus tard, j’accompagnai Lacan lors d’une visite à Heidegger à
Fribourg-en-Brisgau. Il avait appris que ce dernier avait eu un accident
vasculaire cérébral et il souhaitait, selon ses mots, le revoir avant qu’il ne
meure. Il le connaissait de longue date, lui ayant fait une première visite au
début des années 50 avec Jean Beaufret, qui avait été son analysant. Lacan avait
traduit en français un de ses textes, intitulé « Logos », paru en 56 dans la
revue La Psychanalyse. En 55,
Heidegger avait été invité par Beaufret et Maurice de Gandillac à un colloque à
Cerisy-la-Salle. Au retour, Heidegger et sa femme s’étaient arrêtés à
Guitrancourt où ils avaient séjourné quelques jours. Lacan leur avait fait
visiter la région en voiture, à tombeau ouvert comme d’habitude, sans tenir
compte des hauts cris de madame Heidegger.
Nous étions allés
en avion à Bâle, où nous avions visité le très beau musée des beaux-arts, avant
de louer une voiture pour nous rendre à Fribourg où nous étions attendus.
Les Heidegger
habitaient une maison plutôt récente dans un quartier résidentiel, qui ne
ressemblait guère aux images de cabane dans la forêt que j’associais au philosophe.
Nous n’étions pas plus tôt entrés que madame Heidegger nous enjoignit avec
autorité d’utiliser les patins qu’elle réservait aux visiteurs. Je savais, de mes
origines jurassiennes, que c’était d’un usage assez courant dans les régions
montagneuses, à cause de la neige. Dans les pays nordiques, que je connaissais aussi,
on enlève ses chaussures en entrant dans une maison. Mais on était alors en
avril, et je sentis visés en nous les importateurs des salissures du monde
extérieur. Freud m’avait appris que le dehors pour l’inconscient est synonyme
de l’étranger, c’est-à-dire de l’ennemi et de ce qui est en général haïssable. J’étais
partagée entre le sentiment désagréable d’être une intruse et l’hilarité contenue
que suscitait en moi le contraste inattendu entre les patins et la
métaphysique.
Nous fûmes
introduits au salon où Heidegger était étendu sur une chaise longue. Sitôt
assis à ses côtés, Lacan entreprit de lui faire part de ses dernières avancées théoriques
faisant usage des noeuds borroméens, qu’il était en train de développer dans
son séminaire. Pour illustrer son propos, il sortit de sa poche une feuille de
papier pliée en quatre, sur laquelle il dessina une série de noeuds pour les
montrer à Heidegger, qui pendant tout ce temps ne disait mot et gardait les yeux
fermés. Je me demandais si ce dernier exprimait ainsi son absence d’intérêt ou
s’il fallait mettre en cause l’affaiblissement de ses facultés. Lacan, qui n’était
pas homme à renoncer, s’obstinait, la situation menaçait de s’éterniser.
Heureusement, madame Heidegger survint et mit fin à l’ « entretien », au bout d’un
temps mesuré d’avance pour « ne pas fatiguer son mari ». Nous reprîmes sur nos
patins le chemin de la sortie, non sans avoir été conviés à retrouver le couple
un peu plus tard dans un restaurant voisin.
Décidément
tracassée par les patins, aussitôt dehors, je demandai à Lacan si madame
Heidegger avait été nazie. « Bien entendu », me répondit-il. Il était à l’époque
très peu question des rapports de Heidegger avec le nazisme. Le livre de Victor
Farias n’était pas encore paru.
Pendant le
déjeuner, Heidegger se montra un peu plus loquace, mais la conversation fut peu
animée. Lacan, qui lisait l’allemand, ne le parlait pour ainsi dire pas et nos
hôtes possédaient mal le français. Avant de nous séparer, Heidegger me donna
une photographie de lui, format carte postale, au dos de laquelle il écrivit : Zur Erinnerung an den Besuch in Freiburg im
Bu. am 2. April 1975, sans mention de mon nom. J’étais un peu étonnée de
cet autographe pour fan, que je n’avais pas sollicité, mais je le conservai
pieusement. Un de mes patients, qui vit la photographie sur une étagère de ma
bibliothèque, me demanda si c’était mon grandpère.