De l’ontologie apophatique — à partir de la topologie de l’Ab-grund des Seyns (Heidegger) et de
celle du trou du non-rapport sexuel (Lacan)
Résumé :
Je nomme « ontologie apophatique » das Denken des Seyns
(le penser de l’être) de Heidegger qui le développe lui-même comme
topologie de l’être (Topologie des Seyns). Dans le présent
article, je démontre comment Lacan s’en sert pour fonder la psychanalyse de
façon pure, c’est-à-dire de façon à la fois non empirique et non métaphysique,
et comment le penser topologique de l’être peut se schématiser par la
topologie lacanienne du trou.
Table des matières
§ 1. La topologie du trou apophatico-ontologique
§ 2. L’histoire de l’être (Die Geschichte
des Seyns)
§ 3. Un exemple d’expériences cliniques de l’Aufgehen
du trou apophatico-ontologique
§ 4. La temporalité chrétienne
§ 5. La topologie apophatico-ontologique et les
quatre discours
§ 6. La transformation structurale eschatologique
du discours de l’université au discours de l’analyste
§ 7. Au-delà de l’Aufgehen du trou : la
sublimation
§ 8. Le phallus et le trou du non-rapport sexuel
L’année dernière,
je me suis posé ces deux hypothèses : premièrement, la psychanalyse est
une des voies de restauration de notre rapport avec Dieu ; deuxièmement,
tout l’enseignement de Lacan peut être considéré comme des commentaires sur
cette proposition de Hegel : « Das
Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen
Selbstbewußtsein » (la conscience de soi n’atteint sa satisfaction
que dans une autre conscience de soi). Je vais essayer de m’expliquer devant
vous .
§ 1. La topologie du trou apophatico-ontologique
L’expression
« ontologie apophatique » m’a été inspirée par Heidegger qui barre le
mot Sein d’une croix (Durchkreuzung) (cf. fig.
1).
Fig. 1
Ce Sein
barré ne se trouve, parmi ses textes publiés de son vivant, que dans Zur
Seinsfrage (1955). Mais maintenant on peut trouver le Seyn barré
d’une croix (cf. fig. 2) partout dans ses Cahiers noirs de
l’après-guerre.
Fig. 2
Par exemple, il
commence ses Anmerkungen IV en disant ceci (GA 97, p.327) :
Das Denken beginnt indessen, das Denken
des Seyns zu seyn.
Le penser commence en ce qu’il est le
penser de l’être.
Ce qui veut dire
que je pense si et seulement si je pense à l’être, non pas à un étant ni
à l’être non barré, c’est-à-dire l’être métaphysique.
Mais qu’est-ce
que le Seyn ? Puisque la réponse de Heidegger à cette
question n’est pas très claire, je le redéfinirai moi-même comme ceci : le
Seyn est le mathème du
résultat de ce travail qu’il appelle dans son Sein und Zeit
« destruction de la tradition ontologique », c’est-à-dire la
destruction de l’ontologie métaphysique telle qu’Aristote l’a définie comme
« ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν » (une science qui contemple
l’étant en tant qu’étant). Selon Heidegger , la
tradition ontologique a commencé par la pose (Setzung) de l’ἰδέα platonicienne comme τὸ ὄντως ὄν (ce qui est réellement), et s’est achevé avec
l’annonce nietzschéenne de la venue du surhomme (Übermensch) qui incarne
la volonté de puissance (Wille zur Macht). Alors, que trouve-t-on par la
destruction de cette tradition ? Le trou du Seyn que le Sein
métaphysique obturait depuis Platon jusqu’à Nietzsche. Je l’appellerai trou
apophatico-ontologique (sit venia verbo).
Seulement Heidegger ne dit pas Loch (trou) mais Abgrund
(abîme, abysse ou gouffre). Parfois il écrit Ab-grund pour suggérer
qu’il s’agit de l’abîme fondamental ou du fondement abyssal. C’est Lacan qui
utilise le terme « trou », puisqu’on traite une variété de trous dans
la psychanalyse : ceux de la bouche, de l’anus, du regard, du silence et
surtout du manque phallique, c’est-à-dire de la castration que Lacan redéfinira
comme trou du non-rapport sexuel, autrement dit, le trou du phallus impossible
(qui ne cesse pas de ne pas s’écrire).
Bref, le Seyn, c’est le mathème
heideggérien du trou apophatico-ontologique.
Maintenant, à partir de la topologie de cet Ab-grund
des Seyns, on peut schématiser de façon suivante (cf. fig. 3) ce que
Heidegger appelle Kehre von »Sein und Zeit« zu »Zeit und Sein« :
Fig. 3
Dans son Sein und Zeit, pour mettre en question le
sens de l’être, Heidegger part de notre Dasein en tant que nous sommes
là comme un vivant dans ce monde, pour arriver au domaine de l’être comme tel
en traversant la zone problématique de la différence ontologique (la différence
entre l’étant et l’être, laquelle est appelée dans le Sein und Zeit
horizon transcendantal). Mais c’est précisément la question de savoir ce que
serait cette différence ontologique qui le conduit à la Kehre, laquelle
consiste dans ce renversement topologique : maintenant, à partir des Beiträge
zur Philosophie (vom Ereignis), c’est le trou du Seyn qui se
situe dans la localité (Ortschaft) centrale de la topologie. Alors la
différence ontologique se résout dans ce trou même. Et le mouvement du Denken
des Seyns consiste à tourner autour du trou apophatico-ontologique.
Autrement dit, la topologie des Seyns est le foyer du penser de
Heidegger.
Mais parmi tous les lecteurs d’alors de Heidegger, qui
s’est aperçu, au moment de la publication de l’article Zur Seinsfrage en
1955, de l’importance de cette topologie centrale de l’Ab-grund des Seyns
dans le penser heideggérien, si ce n’est Lacan ? Je le dis parce que
je suppose ceci : que Lacan a inventé à partir du Sein son
mathème du sujet barré $ présenté à son auditoire pour la première fois
dans son Séminaire V (1957-1958) Les formations de l’inconscient. Il
faut dire que cela n’est que ma conjecture, puisque je n’ai aucune preuve ni
aucun témoignage qui démontrent cette hypothèse. Mais étant donné que dans la
tradition ontologique l’être (οὐσία), le sujet
(ὑποκείμενον) et la substance (ὑπόστασις) sont quasi-synonymes, il est très
probable que le Sein heideggérien a donné à Lacan l’inspiration
du mathème du sujet barré $.
Fig. 4
Et où Lacan place-t-il ce mathème dans son graphe du
désir (cf. fig. 4) présenté en même temps que le $ dans son Séminaire
V ? Dans la place en bas à droite qui est le point de départ du processus
dialectique. Ce que formalise ce schéma un peu compliqué, c’est essentiellement
ce mouvement du trou du sujet $ qui est le désir – comme Hegel définit
le Selbstbewußtsein comme Begierde ou, pour mieux dire, Urbegierde
(désir originaire) – et qui, partant de là, arrivera finalement non pas à une
satisfaction qui se produirait dans un comblement du trou par le phallus Φ, mais
à un autre trou – ou l’Autre trou – qu’est le S(Ⱥ), le signifiant du manque
dans l’Autre.
Je suggère ici préalablement que ce mouvement du trou du
sujet $ qui aboutit à l’Autre trou S(Ⱥ) est une schématisation de cette
proposition-là de Hegel : « Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem
anderen Selbstbewußtsein », laquelle Befriedigung
(satisfaction) est la jouissance de sublimation du désir qui se produit à la
fin de l’analyse.
Alors, pourquoi
faut-il revenir à la sublimation dont Lacan ne parle plus dans son enseignement
des années 1970 ? Parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel, autrement dit,
que le phallus Φ qui puisse obturer le trou apophatico-ontologique est impossible. Même si
Lacan n’utilise plus ce mot sublimation dans son dernier enseignement,
il continue de parler de l’amour, lequel est défini comme « la sublimation
du désir » dans son Séminaire X (1962-1963) L’angoisse, et qui
figure sous une forme déformée dans le titre de son Séminaire XXIV (1976-1977) L’insu
que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, qui veut dire : L’insuccès de
l’Unbewußt (c’est-à-dire l’inconscient) c’est l’amour. Je vous ferai
remarquer que c’est le seul Séminaire de Lacan qui porte le mot amour
dans le titre. Mais l’insuccès de l’inconscient, qu’est-ce que cela veut
dire ? C’est exactement l’Autre trou S(Ⱥ), que
Lacan appelle aussi « trou du non-rapport sexuel » dans son Séminaire
XXII (1974-1975) R.S.I., à cause de quoi ce que Freud appelle Genitalorganisation,
le supposé stade final de maturation de la pulsion sexuelle, est voué à
l’échec. Alors il n’y a que la sublimation qui puisse mettre fin au mouvement
de l’Urbegierde $. J’y reviendrai.
En tout cas, la position fondamentale du $ dans
son enseignement nous suggère que Lacan s’est bien aperçu dès 1955 de
l’importance de la topologie centrale de l’Ab-grund des Seins
dans le penser de Heidegger. Et comme nous allons le voir, Lacan se sert de la
topologie du trou du sujet $, autrement dit de la topologie du trou
apophatico-ontologique, pour fonder la psychanalyse de façon pure, c’est-à-dire
de façon à la fois non-empirique et non-métaphysique.
Oui, nous pouvons dire que tout l’enseignement de Lacan
consiste à fonder la psychanalyse de façon pure. Maintenant, si quelqu’un vous
pose la question : « Lacan, qui est-il ? », vous pouvez lui
répondre succinctement : si c’est Freud qui est le fondateur de la
psychanalyse, Lacan en est le refondateur. Et nous pouvons le constater à
partir de ces trois citations que je vous présente de façon antichronologique
(c’est moi qui souligne les mots mis en italique) : d’abord il dit dans
son Séminaire XXV (1977-1978) Le moment de conclure qu’« il n’y a
pas de rapport sexuel : c’est le fondement de la psychanalyse » ;
ensuite, il commence son Séminaire XI (1964) Les quatre concepts
fondamentaux de la psychanalyse en disant exactement que « je vais
vous parler des fondements de la psychanalyse » ; et enfin, je
cite ce passage de son Rapport de Rome (1953) : « Elle (la
psychanalyse) ne donnera des fondements scientifiques à sa théorie comme
à sa technique qu’en formalisant de façon adéquate ces dimensions
essentielles de son expérience qui sont, avec la théorie historique du
symbole : la logique intersubjective et la temporalité du sujet. Ramener
l’expérience psychanalytique à la parole et au langage comme à ces fondements,
intéresse sa technique . »
Ainsi, dans l’enseignement de Lacan, il s’agit du fondement pur de la
psychanalyse. Je vous recommande de le relire de ce point de vue-là.
§ 2. L’histoire de l’être (Die Geschichte
des Seyns)
Alors, je reformulerai en termes de trou
apophatico-ontologique ce que Heidegger appelle Geschichte des Seyns
(l’Histoire de l’être) en trois temps de façon suivante :
0) Tout d’abord, le moment archéologique :
Au commencement (ἐν ἀρχῇ ) était ouvert le trou
apophatico-ontologique. On supposerait volontiers un état initial parfait où
rien ne manque comme celui d’Adam et d’Ève dans le jardin d’Éden, mais cela
n’est qu’une mythologie. Il faudrait lire plutôt les deux premiers versets du
premier chapitre de la Genèse :
Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et
les ténèbres à la surface de l’abîme (תְּהוֹם), et l’Esprit de Dieu planait à
la surface des eaux.
Voilà un témoignage de l’ouverture archéologique du trou
apophatico-ontologique à partir duquel se produit la création ex nihilo.
La traduction grecque de ce mot hébreu תְּהוֹם (tehom) dans la Septante
est exactement ἄβυσσος d’où viennent les mots français abysse et abîme,
et la traduction allemande en pourrait bien être Abgrund, bien que
Luther l’ait traduit par Tiefe (profondeur). Heidegger a cherché dans
des fragments de présocratiques un témoignage du Seyn
archéologique qui précédait le Sein métaphysique, tandis que nous
pouvons en trouver un dans la Bible qui nous est beaucoup plus familière que
des présocratiques.
1) Et puis, quand le trou apophatico-ontologique est obturé par l’ἰδέα platonicienne en tant que τὸ ὄντως ὄν, autrement
dit, quand le Sein métaphysique se substitue au Seyn
archéologique, la phase métaphysique commence. L’obturation métaphysique se
maintient par des figures transcendantales qui succèdent à l’ἰδέα platonicienne (par exemple, τὸ ὂν ᾗ ὂν, οὐσία, ἐνέργεια, substantia,
actualitas et le Dieu scolastique en tant que causa sui) jusqu’à l’âge
classique. Dans cette phase, on ne doute pas et ne peut pas douter de leur
transcendance (autrement dit, leur apriorité).
2) Mais quand, vers le milieu du XVIIIème siècle, l’obturation
métaphysique du trou apophatico-ontologique s’annule sous la domination de la
science moderne et du capitalisme, la phase eschatologique commence, laquelle
dure encore aujourd’hui et durera dans cette tension eschatologique qui devient
de plus en plus intolérable, jusqu’au moment eschatologique que Heidegger
appelle Ereignis.
Pourquoi la domination de la science et du capitalisme
induit-elle l’annulation de l’obturation métaphysique ? Parce qu’il est
maintenant évident que ces figures transcendantales qui obturaient le trou
apophatico-ontologique ne sont pas τὸ ὄντως ὄν : pour la science, ce qui
existe vraiment est ce qu’on peut analyser par des moyens scientifiques, y
compris ce qu’on ne peut pas analyser pour le moment à cause de conditions
technologiques, mais qu’on pourra analyser si un certain développement technologique
le permet ; et pour le capitalisme, ce qui existe vraiment est ce qu’on
peut exploiter pour l’accroissement du capital, y compris ce qu’on ne peut pas
exploiter pour le moment à cause de conditions technologiques, mais qu’on
pourra exploiter si un certain développement technologique le permet. Or, ces
figures métaphysiques ne sont pas analysables scientifiquement ni exploitables
capitalistiquement ; donc elles n’existent pas.
Ainsi, à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle,
l’obturation métaphysique du trou apophatico-ontologique ne peut plus se
maintenir comme une présupposition évidente et inquestionnable. Alors, le trou
veut s’ouvrir en surgissant et surgir en s’ouvrant (aufgehen). Et cet Aufgehen
se signale par l’angoisse dont nous savons à partir de l’expérience
psychanalytique qu’il s’agit de l’angoisse face au néant (y compris le non-sens
et l’incertitude), de celle face à la mort et de celle face au péché en fonction
du trou qui s’ouvre comme trou du néant, celui de la mort et celui du péché.
Alors cette angoisse provoque des formes diverses de
résistance et de défense, comme nous le montre l’expérience psychanalytique.
Mais dans l’histoire de la philosophie, qu’est-ce qui se passe à ce moment-là,
c’est-à-dire dans la seconde moitié du XVIII siècle ? La pose (Setzung)
kantienne de la raison pure qui doit obturer encore une fois le trou
apophatico-ontologique pour que la certitude et la vérité de la connaissance
scientifique soient garanties. Et Kant ne suppose pas cette figure
transcendantale tout naïvement, mais il la pose en en examinant critiquement la
nécessité. Cette sorte de défense par la réobturation métaphysique du trou
continue jusqu’à das transzendentale Ich de Husserl.
Cependant c’est chez Nietzsche, ce penseur qui a proclamé
la mort du Dieu éternel et la venue du surhomme incarnant la volonté de
puissance, que Heidegger voit l’achèvement (Vollendung) de la
métaphysique, ce qui veut dire ceci :
Nietzsche
pense par avance, dans sa pensée de la volonté de puissance, ce qu’est le
fondement métaphysique de l’achèvement de la Neuzeit .
Dans la pensée de la volonté de puissance s’achève par avance le penser
métaphysique même. Nietzsche, le penseur de la pensée de la volonté de
puissance, est le dernier métaphysicien de l’Occident. L’époque dont
l’achèvement se déploie dans sa pensée, la Neuzeit, est une Endzeit ,
c’est-à-dire, une époque où, à un certain moment et d’une certaine manière,
s’élève la décision historique sur ceci : si cette Endzeit est la
clôture de l’histoire occidentale ou bien le contrejeu à un autre commencement.
Parcourir la démarche de pensée nietzschéenne jusqu’à la volonté de puissance,
cela signifie ceci : aborder de front cette décision historique.
Le fait que les
figures idéales traditionnelles aient perdu leur efficace pour obturer le trou
apophatico-ontologique, se traduit par la dévalorisation des valeurs suprêmes (Entwertung
der obersten Werte), c’est-à-dire le nihilisme . Si on
ne fait que déplorer cette perte de façon pessimiste, on est dans le nihilisme
passif qui entraînerait la fin de l’histoire occidentale. En revanche, si on
ose poser une nouvelle valeur à la place des valeurs perdues, on est dans le
nihilisme actif qui ferait le contrejeu (Gegenspiel, autrement dit,
résistance et défense) à l’autre commencement, c’est-à-dire au moment
eschatologique de l’Histoire de l’être. La volonté de puissance est
exactement cette volonté de poser une nouvelle valeur de sorte que toutes les
valeurs existantes soient renversées (Umwertung der aller Werte), ce qui
veut dire au fond que le platonisme soit renversé (Umdrehung des Platonismus)
pour que maintenant se pose, à la place de l’ἰδέα mythologique, la vie réelle qui voudrait devenir toujours plus puissante
qu’elle-même (Machtsteigerung : accroissement de puissance).
Ainsi, la volonté
de puissance est un renversement du platonisme au sens où maintenant le devenir
se substitue à l’être (Dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen :
empreindre sur le devenir le caractère de l’être). C’est-à-dire, maintenant, ce
qui obture le trou apophatico-ontologique, n’est plus quelque chose d’éternel
et d’immuable comme l’est l’ἰδέα platonicienne, mais la volonté de
puissance qui veut et doit devenir toujours plus puissante qu’elle-même. Et
c’est en tant qu’incarnation de la volonté de puissance que Nietzsche présente,
par la bouche de Zarathoustra, le surhomme qui doit venir prochainement.
Mais il est
évident qu’une personne en tant qu’individu ne peut pas être surhomme, puisque
quelqu’un qui tente de l’être tombera nécessairement dans l’épuisement. Et
l’idée qu’un jour surgira une nouvelle « race » surhumaine n’est
évidemment que fantasmatique, voire paranoïaque si on en a la conviction comme
Nietzsche.
Certes, on
pourrait imaginer que Nietzsche aurait pu trouver, s’il avait lu Marx, un
exemple concret du surhomme dans le capitaliste en tant que personnification du
capital qui poursuit sans cesse l’accroissement du capital sous la pulsion
absolue d’enrichissement (der absolute Bereicherungstrieb). Mais il faut
dire qu’il est maintenant indéniable que le capitalisme entraînera l’épuisement
des ressources naturelles et la dégradation environnementale de la Terre, et
par là le dépérissement de l’humanité tout entière.
Le concept
nietzschéen du surhomme incarnant la volonté de puissance est déjà assez
paranoïaque, et ce sans aucune corrélation avec l’encéphalopathie qui a
entraîné de façon aiguë son Umnachtung. Depuis, nous observons que des
idéologies qui, après la volonté de puissance, se sont posées et se posent pour
obturer le trou apophatico-ontologique, par exemple le communisme, des formes
diverses de nationalisme, de racisme et de sexisme (y compris le masculinisme
et le patriarcalisme), deviennent de plus en plus paranoïaques. Et à partir du
mois de janvier 2025, ces quatre pays les plus puissants parmi les grandes
puissances, c’est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde sont
tous gouvernés par des hommes paranoïaques. Quelle horreur !
Cette
paranoïsation globale et généralisée est le produit de la réaction défensive
contre l’angoisse de l’Aufgehen du trou apophatico-ontologique. Plus cet
Aufgehen est imminent, plus la situation est paranoïqaue. Cette
situation de plus en plus intolérable durera jusqu’au moment eschatologique d’Ereignis.
§ 3. Un exemple d’expériences cliniques de l’Aufgehen
du trou apophatico-ontologique
L’Aufgehen
(ouverture-surgissement) du trou apophatico-ontologique nous provoque
l’angoisse que Heidegger appelle Grundbefindlichkeit ou Grundstimmung.
Elle nous est fondamentale pour autant que nous somme dans la phase
eschatologique où le trou veut toujours s’ouvrir et surgir devant nous.
L’expérience psychanalytique nous montre qu’en général, cette angoisse prend
une ou plusieurs de ces trois formes : les angoisses du néant, de la mort
et du péché.
Pour voir comment
se manifeste l’Aufgehen du trou apophatico-ontologique dans
l’expérience, nous réexaminons cet exemple princeps de l’interprétation du
rêve, c’est-à-dire le rêve de l’injection faite à Irma que Freud a eu dans la
nuit du 23/24 juillet 1895.
Un grand hall – beaucoup d’invités que nous recevons. – Parmi eux, Irma, que je prends aussitôt à
part pour répondre à sa lettre, lui faire des reproches pour n’avoir pas encore
accepté la « solution ». Je lui dis : Si tu as encore des
douleurs, ce n’est vraiment que de ta faute. – Elle répond : Si tu savais ce que
j’ai à présent comme douleurs à la gorge, à l’estomac et au ventre, ça me serre
de partout. – Je
suis effrayé et la regarde. Elle a un air pâle et bouffi ; je pense
finalement que j’omets quand même de voir là quelque chose d’organique. Je
l’emmène à la fenêtre et regarde dans sa gorge. À ce moment-là, elle se montre quelque peu
récalcitrante, comme les femmes qui portent un appareil dentaire. Je pense en
moi-même : elle n’en n’a pas besoin. – Du reste, la bouche s’ouvre alors très
bien et je trouve à droite une grande tache blanche, et ailleurs je vois sur de
curieuses formations frisées, manifestement formées sur le modèle des cornets
du nez, des escarres étendues d’un blanc grisâtre. – J’appelle vite en consultation le Dr M.,
qui répète l’examen et confirme… Le Dr M. a un tout autre air que
d’habitude ; il est très pâle, boite, a le menton sans barbe… Maintenant
mon ami Otto se tient aussi debout à côté d’elle, et l’ami Leopold la percute à
travers son corset et dit : elle a une matité en bas, à gauche, il montre
aussi une partie cutanée infiltrée à l’épaule gauche (ce que, malgré le
vêtement, je sens comme lui)… M. dit : Pas de doute, c’est une infection,
mais ça ne fait rien ; il va s’y ajouter de la dysenterie et le poison va
s’éliminer… Nous savons aussi immédiatement d’où provient l’infection. L’ami
Otto lui a administré il y a peu, alors qu’elle ne se sentait pas bien, une
injection avec une préparation de propyle, propylène… acide propionique…
triméthylamine (dont je vois la formule en caractère gras devant moi)… On ne
fait pas de telles injections avec une telle légèreté… Il est vraisemblable
aussi que la seringue n'était pas propre…
Du point de vue
apophatico-ontologique, il est tout à fait évident que la bouche grand ouverte
d’Irma représente l’Aufgehen du trou (en effet, nous pouvons remarquer dans
cette phrase « Der Mund geht dann auch gut auf »
[ la bouche s’ouvre alors très bien ] le verbe aufgehen), et ce en tant
que trou du péché comme le suggèrent les paroles de reproche : « ce
n’est vraiment que de ta faute » (es ist wirklich nur deine Schuld)
et le doute d’une erreur de diagnostic. Et en effet, comme on le sait, l’étude
biographique faite par Masson à
partir des lettres de Freud à son ami Wilhelm Fliess met au jour ce qu’il y a
vraiment eu lieu dans l’arrière-plan de ce rêve : la faute grave de Fliess
dans son opération nasale faite vers le 21 février 1895 (c’est-à-dire cinq mois
avant le rêve d’Irma) à l’endroit d’une des analysantes de Freud, Emma
Eckstein, qui a failli mourir au début du mois suivant à cause de l’hémorragie
massive résultante de ladite faute. Donc il ne s’agit pas d’une faute médicale
de Freud lui-même, mais de l’ORL berlinois. Cependant, puisque c’est bien lui
qui a persuade sa patiente de se faire opérer par Fliess, il se culpabilise
tout d’abord. Mais ensuite, pour nier la responsabilité de son ami, il finit
par refouler sa propre culpabilité et culpabiliser la victime, ce qui est
représenté dans le rêve par ces paroles : « ce n’est vraiment que de ta
faute ». Pourtant ce qui est refoulé revient effectivement sous cette
forme de l’Aufgehen du trou du péché.
Cet Aufgehen
devrait lui provoquer une grande angoisse, ce qui n’a pas lieu. Pourquoi ?
Parce que le trou est réobturé en deux temps : d’abord sont mobilisés ses
trois amis, le Dr M (Joseph Breuer), Otto et Leopold, qui déroulent une scène
ridicule autour d’Irma. Mais à la fin, ce qui apparaît comme un deus ex
machina, c’est la formule chimique de la triméthylamine fort accentuée en étant
imprimée en caractère gras (fettgedruckt). Seulement la formule dont il
s’agit n’est pas celle que nous nous représentons aujourd’hui (cf. fig. 5),
mais celle que Lacan nous présente dans la séance du 9 mars 1955 de son
Séminaire II (cf. fig. 6). Peut-être autrefois, c’était ainsi qu’on présentait
des formules chimiques dans les imprimés.
La triméthylamine
se trouve en effet dans le corps vivant comme un des métabolites intermédiaires
de la choline. Fliess pensait qu’elle devait avoir une place dans la biochimie
des activités sexuelles, ce qui a sans doute motivé l’apparition de la formule
dans le rêve de Freud. Cependant, déjà dans son Séminaire II, Lacan dit que
cette formule est faite « de signes sacrés » puisque la structure
trinitaire y est multipliée. Et c’est Gérard Haddad qui
nous explique pleinement ce qu’elle symbolise. Présentée ainsi (cf. fig. 7), la
formule de la triméthylamine est semblable à la lettre hébraïque ש (shin), laquelle est l’initiale
du mot שֵׁם (shem : nom). Et ce mot avec l’article défini הַשֵּׁם
(HaShem : le Nom) est dans le judaïsme un des noms substitutifs de Dieu יהוה
(YHWH), lequel nom, son nom propre, est déclaré ineffable par la Torah. En
plus, la lettre ש est aussi l’initiale du mot שַׁדַּי (Shaddai : Παντοκράτωρ,
Tout-Puissant) qui est un autre nom substitutif de YHWH.
Fig. 7
Alors nous pouvons avoir cette interprétation topologique : la formule
de la triméthylamine représente par sa similitude avec la lettre ש le Nom de
Dieu, c’est-à-dire, dans la terminologie lacanienne, le Nom-du-Père ou le
signifiant maître S1, qui réobture le trou du péché s’ouvrant devant
Freud sous la forme de la bouche béante d’Irma. En effet, l’obturation du trou
apophatico-ontologique est la fonction du Nom-du-Père comme le suggère cette
remarque de Lacan dans son écrit D’une question préliminaire à tout
traitement possible de la psychose : « le trou [est] creusé dans
le champ du signifiant par la forclusion du Nom-du-Père . » Si
la forclusion du Nom-du-Père creuse le trou, sa restauration l’obture de
nouveau. Et c’est grâce à cette réobturation du trou par le Nom que le rêve
d’Irma n’angoisse pas tellement Freud ni lui déclenche la psychose.
Mais cette
réobturation du trou par le Nom n’est qu’une défense contre l’Aufgehen
angoissant du trou, tandis que cet Aufgehen est nécessaire dans la phase
eschatologique de l’histoire de l’être pour que se produise le moment
eschatologique d’Ereignis. Il ne nous faut pas y résister, mais y être
obéissants pour que l’Ereignis s’approprie (sich aneignen) notre Dasein
et que nous devenions nous-même Ereignis selon la nécessité de
l’histoire de l’être.
Ainsi, l’histoire
de l’être et le processus de l’expérience psychanalytique concordent, et
ce sur le modèle du processus dialectique de la Phénoménologie de l’Esprit,
puisque Heidegger et Lacan se réfèrent, tous les deux, à Hegel pour penser au
mouvement et au changement dialectiques de l’être et du sujet $.
§ 4. La temporalité chrétienne
Comme on le sait, Hegel était luthérien. À l’Université de Berlin, il faisait à peu près tous les
trois ans (1821, 1824, 1827 et 1831) ses Leçons sur la philosophie de la
religion. Et là il dit en 1824 : « L’objet de la religion ainsi
que de la philosophie est la vérité éternelle dans son objectivité même, Dieu
et rien que Dieu, et l’explication de Dieu », et en 1827, il dit
encore : « Dans la philosophie, laquelle est théologie, il s’agit
uniquement et seulement de présenter la raison [Vernunft] de la religion. »
Ainsi, pour lui, la philosophie et la théologie sont la même chose, ce qui veut
dire que, quand il pense, il pense à Dieu. De Heidegger et de Lacan qui
appartiennent, tous les deux, à la tradition catholique, nous pouvons dire
aussi la même chose : quand ils pensent, ils pensent à Dieu. C’est assez
évident chez Lacan, puisque, par exemple, le Nom-du-Père est un des mots-clefs
de son enseignement, et qu’il met en équivalence dans un passage
de sa Télévision l’« être un saint » et l’« être un
psychanalyste », lequel passage, pour autant que je sache, n’a jamais été
commenté suffisamment en relation avec les quatre discours. Encore nous pouvons
nous apercevons maintenant que, quand il dit que « l’inconscient
est le discours de l’Autre » et que « le désir de l’homme est le
désir de l’Autre » et quand il met l’Autre dans une relation avec le sujet
dans ses schémas L et R (cf. fig. 8 et 9), cet Autre n’est rien d’autre que
Dieu, ce qui est indiqué clairement par la même position de l’Autre et le
Nom-du-Père dans le schéma R. Et s’il s’intéresse particulièrement au cas du
président Schreber, c’est parce qu’il s’agit là, dans son délire, explicitement
de son rapport sexuel avec Dieu.
Quant à Heidegger, il dit par exemple ceci :
Le Dieu [ der
Gott ] vient dans la philosophie par l’Austrag ,
lequel nous pouvons d’abord penser comme le lieu préalable [Vorort] de
l’essence de la différence de l’être et de l’étant. Cette différence fait la
fente fondamentale [Grundriß] dans la structure de l’essence de la
métaphysique. L’Austrag produit et donne l’être comme fondement de
pro-duction [ her-vor-bringender Grund ], lequel fondement
lui-même requiert, à partir de ce qui est fondé par lui, le fondement
convenable pour lui, c’est-à-dire la causation par la chose la plus
fondamentale. C’est la cause en tant que causa sui. Et c’est le nom
juste du Dieu dans la philosophie. Ce Dieu, l’homme
ne peut pas Le prier, ni Lui faire d’offrande. Devant la causa sui,
l’homme ne peut pas tomber à genoux par crainte, ni musiquer ou danser devant
ce Dieu.
Par conséquent,
le penser a-thée [ das gott-lose Denken ],
lequel doit rejeter le Dieu de la philosophie, le Dieu en tant que causa sui, est peut-être plus proche du Dieu divin [ der
göttliche Gott ]. Cela veut dire ici simplement : il est plus
libre pour Lui que l’onto-théo-logique voudrait l’admettre.
Ainsi, il nous faut distinguer ces deux Dieux, le « Dieu de la
philosophie » et le « Dieu divin », ou pour mieux dire,
distinguer le vrai Dieu et cette idole qu’est le Dieu scolastique. Et c’est
exactement ce qu’a fait Blaise Pascal dans son expérience mystique de la
« Nuit du feu » en disant qu’il croit en « Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob, non [ au Dieu ] des philosophes et des
savants. » C’est-à-dire qu’il faut que le Dieu métaphysique soit rejeté,
ou, dans la terminologie lacanienne, forclos, parce qu’il est une idole faisant
obstacle à l’accès au Dieu réel qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.
Donc eux, Hegel, Heidegger et Lacan, quand ils pensent, ils pensent à Dieu.
Alors, qu’est-ce que cela nous apporte quand nous les lisons ? C’est la
temporalité chrétienne, ou, parce que je suppose qu’aussi le judaïsme et
l’islamisme la partagent, il serait mieux de l’appeler temporalité monothéiste.
Et en quoi consiste-elle ? En ceci qu’elle comporte non seulement le temps
au sens ordinaire ou aristotélicien, c’est-à-dire le temps de l’Histoire ou le
temps physique, mais aussi bien le moment archéologique de la création ex
nihilo et le moment eschatologique de la consummatio saeculi
(consommation des siècles), lesquels deux moments ne se situent pas sur l’axe
du temps, ce que Heidegger appelle, comme nous le verrons ci-dessous, ekstatisch
(extatique). Cette temporalité chrétienne est suggérée dans la Bible par cette
expression qui se trouve dans le livre de l’Apocalypse : ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ
ἐρχόμενος, et qui veut dire ceci : Dieu, Celui qui existe dans le
temps de l’Histoire, qui était au moment archéologique de la création ex nihilo,
et qui viendra au moment eschatologique du jour du Seigneur.
Cette temporalité chrétienne est formulée dans la dialectique hégélienne
par ces trois temps : d’abord l’immédiateté archéologique, ensuite
l’aliénation actuelle, et enfin la réflexion eschatologique en soi-même [ Reflexion
in sich selbst ] par laquelle se produit l’être absolument médié [ das
absolut vermittelte Sein ].
Quant à Heidegger, dans son cours du
semestre d’été de 1927 intitulé Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie,
c’est-à-dire quelques mois après la publication de son magnum opus, il définit
la temporalité [Zeitlichkeit] de façon plus claire que dans Être et
temps en disant ceci : « Comme l’unité extatique de l’avenir, du
passé et du présent [ ekstatische Einheit von Zukunft, Gewesenheit und
Gegenwart ], la temporalité a un horizon déterminé par l’extase. La
temporalité est, comme l’unité originaire de l’avenir, du passé et du présent [ die
ursprüngliche Einheit von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart ], en
soi-même, extatique-horizontal . »
Il me semble que cette expression heideggérienne de « die Einheit von
Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart » vient directement de cette expression
biblique de « ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος »
où Jean de Patmos utilise ce quasi-néologisme de « ὁ ἦν » (le
« il était »), tout comme Heidegger ne dit pas simplement « Vergangenheit »
mais ce quasi-néologisme de « Gewesenheit ». Puisque Heidegger
dit expressément que « ‹ être › dans Être
et temps n’est rien d’autre que ‹ temps › pour autant que le
mot ‹ temps › est utilisé comme le nom
préalable de la vérité de l’être »
et qu’il dit aussi que ces trois questions – la question du sens de l’être (Frage
nach dem Sinn von Sein), la question de la vérité de l’être (Frage nach
der Wahrheit des Seins) et la question du lieu ou de la localité de l’être
(Frage nach dem Ort oder der Ortschaft des Seins), autrement dit la
topologie de l’être (Topologie des Seins que Heidegger écrit dans ses
cahiers noirs d’après-guerre Topologie des Seyns [ topologie
de l’être ]) – se posent successivement sur le même chemin du
penser ,
ce chemin qui mène à l’abîme de l’être c’est-à-dire au trou
apophatico-ontologique, maintenant nous pouvons voir comment la notion de
temporalité dans Être et temps aboutit au trou de l’être :
c’est parce qu’elle consiste dans le « ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος »
qui comporte non seulement l’être présent (Anwesenheit) mais aussi bien
le non-être du moment archéologique de la création ex nihilo et le
non-être du moment eschatologique de la consummatio saeculi, que la
question de la temporalité mène Heidegger au trou de l’être qui est la
condition de la possibilité de l’être en tant que présence.
§ 5. La topologie apophatico-ontologique et les
quatre discours
Alors, où pouvons-nous trouver chez Lacan la formulation la plus claire de
cette temporalité chrétienne ? Je pense que c’est dans les quatre discours
(cf. fig. 10), surtout dans le processus de transformation qui part du discours
du maître et qui aboutit, en passant par le discours de l’université, au
discours de l’analyste.
Fig. 10
La schématisation des quatre discours est la plus achevée et la plus belle
et donc la plus puissante parmi les schémas lacaniens que j’appelle
mathématico-topologiques, puisque dans ces schémas-là – le schéma optique avec deux miroirs, les schémas L et R,
le graphe du désir et les quatre discours – un certain nombre de mathèmes sont disposés dans des
places topologiquement définies.
Les quatre discours peuvent être mis en relation avec la topologie du plan
projectif, alias le cross-cap (cf. fig. 11, 12 et 13) que Lacan
introduit dans son enseignement au moment du Séminaire IX (1961-1962) L’Identification
pour penser mieux à la topologie du trou apophatico-ontologique et la
schématiser mieux.
Quand on identifie le bord du trou creusé dans une sphère
(cette sphère trouée est homéomorphe à un disc) et le bord d’une bande de
Möbius (cf. fig. 11), on obtient une surface close qu’on appelle plan projectif
(cf. fig. 12 et 13), lequel s’appelle ainsi à cause de son rapport avec la
géométrie projective, mais je n’y entrerai pas ici. Comme on le voit dans les
figures 12 et 13 (que Lacan appelle parfois asphère), le plan projectif
en tant que surface close n’est pas représentable de façon adéquate dans
l’espace euclidien de dimension 3, mais on ne peut y voir que la surface de
sphère trouée (bleu) et le bord d’identification (vert), tandis que la surface
möbiusienne (rouge) déborde l’espace de dimension 3. Dans la terminologie
mathématique, on dit que le plongement (embedding) du plan
projectif dans l’espace euclidien de dimension 3 est impossible, et que le cross-cap
ou l’asphère (cf. fig. 12 et 13) sont une des manières possibles d’immersion
du plan projectif dans l’espace euclidien de dimension 3. De toute façon, par
l’opération inverse, c’est-à-dire si l’on coupe le plan projectif d’une manière
convenable, on obtient une sphère trouée et une bande de Möbius.
Comme nous le voyons, la topologie du plan projectif ne nous est pas facile
à représenter ni à manier. Alors, Lacan nous introduit dans son Séminaire XI
(1964) Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse le schéma de
deux cercles qui ressemble à un diagramme de Venn (cf. fig. 14) mais qui n’a
rien à faire avec la théorie des ensembles.
Comme le montre cette juxtaposition
de la figure 11 et la figure 14, le schéma de deux cercles est une
schématisation plus claire et plus maniable de la topologie du plan projectif,
où le trou apophatico-ontologique (blanc) se situe au centre avec son bord
(vert), la surface de la sphère trouée (bleu) à droite et la surface
möbiusienne (rouge) à gauche.
Alors, quelle est la correspondance entre la topologie du plan projectif et
les quatre discours ?
Fig. 15
Prenons pour exemple la correspondance entre le schéma de
l’aliénation et le discours de l’université (cf. fig. 15), lesquels,
l’aliénation et le discours de l’université, sont notre mode d’existence
quotidien. Seulement je dois vous dire que ce schéma de l’aliénation n’est pas
exactement ceux que Lacan nous présente dans ses Séminaires XI (la séance du 27
mai 1964) et XIII (la séance du 15 décembre 1965), mais une reconstruction à
partir des schémas originaux et de tentatives de Jacques-Alain Miller qui a
essayé à de certains moments de son cours L’Orientation lacanienne de
situer les mathèmes des quatre discours dans le schéma de deux cercles.
D’abord, dans le schéma de l’aliénation, le trou central qui représente le
trou apophatico-ontologique est obturé par le signifiant maître S1
(jaune). Or, dans le discours de l’université, il est à la place de la vérité,
cette vérité étant la vérité au sens métaphysique qui remonte jusqu’à l’ἰδέα platonicienne.
Donc la place de la vérité est la place de ce qui obture le trou. Comme vous le
remarquez, dans mes figures, la couleur du trou est blanche quand il est ouvert,
tandis que, quand il est obturé, la couleur de ce qui l’obture est jaune.
Ensuite il nous faut prêter attention au bord du trou (vert), comme Lacan
nous dit souvent de le faire. Dans le schéma de l’aliénation, le bord du trou joint la surface de la sphère trouée (bleu) et celle de
la bande de Möbius (rouge). Et ce qui fait le bord est l’objet a. Quand
Lacan dit parfois que l’objet a est le trou, il veut dire, me
semble-t-il, que l’objet a fait le bord du trou. Dans le discours de
l’université, l’objet a est à la place de l’autre. Donc la place de
l’autre est la place de ce qui fait le bord du trou.
Troisièmement, la surface de la sphère trouée (bleu) est, comme on le voit
dans les figures 12 et 13, presque tout ce qui se trouve du plan projectif dans
l’espace euclidien de dimension 3. Selon l’expression de Lacan dans son
Séminaire XXII (1974-1975) R.S.I., elle donne au plan projectif la consistance
de l’étant (Seiendes). Ce qui fait cette surface est le S2,
lequel se situe dans le discours de l’université à la place de l’agent. Donc la
place de l’agent est la place de la consistance de l’étant.
Enfin, la surface de la bande de Möbius (rouge) est, comme on le voit
également dans les figures 12 et 13, hors de l’espace euclidien de dimension 3,
c’est-à-dire, aussi selon l’expression de Lacan dans son Séminaire R.S.I.,
elle ex-siste à cet espace-là. Ce qui fait la bande de Möbius est le
sujet $, lequel se situe dans le discours de l’université à la place de
la production. Donc la place de la production est la place de l’ex-sistence.
Soit dit en passant, quand nous lisons dans le premier paragraphe du Séminaire
sur « La Lettre volée » cette remarque de Lacan qui nous dit que
le sujet de l’inconscient est à situer dans la place de l’ex-sistence ,
il nous est maintenant clair qu’il pense à la structure qu’il appellera
aliénation et discours de l’université, laquelle structure est, comme je l’ai
déjà dit, notre mode d’existence quotidien.
Maintenant nous pouvons schématiser avec les schémas de deux cercles les
quatre discours (cf. fig. 10) de façon suivante (cf. fig. 16).
Fig. 16
Au commencement, c’est-à-dire au moment archéologique de l’Histoire de l’être,
il y avait le discours du maître où le trou apophatico-ontologique était ouvert
en tant que le trou du sujet $ même. Ensuite, le discours de
l’université arrive quand la phase métaphysique commence par l’obturation du
trou avec le signifiant maître S1, lequel signifiant est ainsi le
mathème de toutes ces figures métaphysiques depuis l’ἰδέα de Platon
jusqu’à la volonté de puissance de Nietzsche. Mais quand la phase
eschatologique commence où l’obturation métaphysique du trou perd son efficace,
le trou veut s’ouvrir et surgir (aufgehen) pour que le discours de
l’analyste se produise. Comme vous le voyez dans la figure 16, dans le discours
de l’analyste, les deux cercles se séparent pour que le sujet $
apparaisse en faisant le bord du trou. C’est ce que Lacan appelle séparation
dans le Séminaire XI et dans l’écrit qu’il rédige dans le cours de ce
séminaire, la Position de l’inconscient. Mais à peine se produit la
séparation, que le trou s’obture de nouveau, de sorte qu’il y ait des
va-et-vient incessants entre l’aliénation (le discours de l’université) et la
séparation (le discours de l’analyste). C’est ce que Lacan appelle pulsation
temporelle également dans le Séminaire XI et dans la Position de
l’inconscient. Mais enfin le moment arrivera où non seulement le discours
de l’analyste s’établit, mais où la jouissance de sublimation se produit aussi
bien. Alors ce sera le moment eschatologique d’Ereignis qui est le
moment de la fin de l’analyse (j’y reviendrai). Quant au discours de
l’hystérique, ce qui le caractérise est l’obturation du trou par l’objet a
pour autant que l’hystérique s’en refuse la jouissance pour que son désir $
reste insatisfait, comme l’indiquent la « spirituelle bouchère » et
son amie : l’objet de refus de celle-ci est le saumon fumé, tandis que
celui de celle-là est le caviar .
Alors, j’ajouterai ici quelques remarques, puisque ces schématisations
éclairent quelques points de l’enseignement de Lacan, notamment de son
enseignement des années 1970. Premièrement, la topologie dont il s’agit dans la
psychanalyse est tétradique (cf. fig. 17), non pas triadique, comme le
suggèrent les quatre places des quatre discours et l’introduction du nœud
borroméen à quatre ronds de ficelle
(cf. fig. 18) dans le Séminaire XXII (1974-1975) R.S.I.
Certes la triade
du symbolique, de l’imaginaire et du réel est fondamentale, mais il faut
distinguer deux définitions du réel : le réel en tant que ce qui ne cesse
pas de ne pas s’écrire, c’est-à-dire l’impossible (rouge), et le réel en tant
que ce qui ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire le nécessaire (vert).
D’ailleurs cette définition-ci est déjà suggérée par la définition du réel
comme ce qui revient toujours à la même place, laquelle définition est élaborée
dans ses Séminaires II et III. Ainsi, la triade lacanienne classique du
symbolique (ce qui se situe à la place du trou, autrement dit à la place de ce
qui obture le trou), de l’imaginaire (ce qui se situe à la place de la
consistance) et du réel (en tant que ce qui se situe à la place de
l’ex-sistence, autrement dit à la place de l’impossible) doit être complétée
par le quatrième élément qui est le réel en tant que ce qui se situe au bord du
trou, autrement dit à la place du nécessaire, et que Lacan choisit dans son
Séminaire XXIII (1975-1976) sur James Joyce d’appeler sinthome, lequel
est l’orthographe du mot symptôme vers l’an 1500, et un homophone de saint
homme dont Lacan lui-même nous rappelle qu’il a parlé du saint dans la Télévision
pour autant que l’« être un saint » et l’« être un
psychanalyste » sont équivalents l’un à l’autre. J’y reviendrai.
Deuxièmement, les correspondances des mathèmes utilisés dans le graphe du
désir (cf. fig. 4) et ceux utilisés dans les quatre discours (cf. fig. 15).
D’abord, le mathème du sujet $ est toujours le même : le mathème du
trou apophatico-ontologique et celui de l’Urbegierde (désir originaire).
En revanche, le mathème A (le grand A) nécessite beaucoup de commentaires. Le
grand A dans les schémas L et R (les figures 8 et 9) est le mathème de l’Autre
symbolique qui correspond au mathème S1 dans le discours de l’université.
Mais dans le Séminaire V (1957-1958) où Lacan nous présente le graphe du désir
pour la première fois et au cours duquel il écrit D’une question
préliminaire à tout traitement possible de la psychose, il distingue deux
Autres, et cette distinction est reprise dans la Subversion du sujet :
1) l’Autre en tant que lieu du signifiant, autrement dit l’ensemble des
signifiants, mais qui comporte le trou du manque, correspond au mathème S2 ; 2) l’Autre-de-l’Autre, c’est-à-dire le Nom du
Père, qui est le signifiant manquant dans l’Autre, correspond au mathème S1.
Alors l’Autre en tant que lieu du signifiant se réduit, puisqu’il a le trou du
manque, au corps maternel qui comporte le trou de castration, c’est-à-dire à la
consistance de l’imaginaire, tandis que l’Autre symbolique est
l’Autre-de-l’Autre qui manque dans l’Autre en tant que lieu du signifiant. Cet
Autre-de-l’Autre figure dans le graphe du désir comme le trou du signifiant
manquant Ⱥ. Le mathème S(Ⱥ), défini comme signifiant du manque dans l’Autre ,
correspond au bord du trou apophatico-ontologique, c’est-à-dire à la place de
l’autre (la place en haut à droite) dans les quatre discours. Le mathème de la
pulsion ($ ◊ D) où le D est défini comme la demande pulsionnelle (Triebanspruch)
est aussi un mathème du trou apophatico-ontologique pour autant qu’il s’ouvre,
bordé de l’objet a, quand l’obturation du trou par le signifiant maître
S1 devient inefficace. Le mathème du fantasme ($ ◊ a) présenté comme une formation imaginaire, est le mathème
de ce qui dissimule le trou, mais, quand même, nous pouvons trouver là aussi
une certaine représentation du trou.
Troisièmement, la transformation
structurale du discours du maître au discours de l’université schématise ce que
Freud appelle Urverdrängung (refoulement originaire ou
archi-refoulement) (cf. fig. 19) et qui
consiste en ceci : au commencement de la phase métaphysique de l’Histoire
de l’être, le signifiant maître S1, en obturant le trou,
refoule le sujet $ en tant qu’Urbegierde dans la place de
l’ex-sistence. Et non seulement il le refoule, mais il s’y substitue, ce en
quoi consiste l’aliénation.
Quatrièmement, cette transformation structurale (cf. fig. 19) formalise le
mythe freudien du meurtre de l’Urvater (père primitif ou patriarche) et,
par là, met au jour la vérité de ce mythe. Le discours du maître correspond à
l’état originaire de la horde primitive où, étant donné qu’il n’y a pas encore
le tabou de l’inceste, l’Urvater S1 à la place de l’agent, en
tant que maître absolu et avide, possède sexuellement toutes les femmes de sa
horde, c’est-à-dire qu’il seul jouit de toutes les femmes, c’est-à-dire de la
Femme. Et puis, le meurtre apporte cette transformation où les fils S2
usurpent la place de l’agent en détrônant le père mort S1 dans la
place de la vérité, et en même temps, ils s’identifient à lui en mangeant sa
chair. Mais à ce moment-là, ils entrent sous la domination du père mort, comme
le moi sous la domination du surmoi. L’Urbegierde (désir originaire) $
est refoulée (Urverdrängung), et les fils ne peuvent pas jouir de la
Femme, mais seulement du plus-de-jouir d’objets prégénitaux a. Tel est
le discours de l’université. Cependant, en formalisant ainsi, nous nous
apercevons que la jouissance parfaite et complète de l’Urvater n’est
qu’un mythe, puisque dans le discours du maître le trou n’est pas du tout
comblé. Il faut nous souvenir qu’au moment archéologique de la création ex
nihilo, l’Éden n’existe pas encore, mais que l’Esprit de Dieu seul plane
sur le trou abyssal. Le mythe de l’Urvater mythifie dans la forme
inverse l’impossibilité de la jouissance du rapport sexuel avec la Femme.
Cinquièmement, puisque j’ai fait allusion au moi et au surmoi, je vous
présente ici la seconde topique de Freud en en situant les instances dans le
schéma de l’aliénation et le discours de l’université (cf. fig. 20) : le S2
est le moi, le S1 le surmoi, le $ le ça et le petit a
l’objet libidinal.
§ 6. La transformation structurale eschatologique
du discours de l’université au discours de l’analyste
Alors, entrons dans les détails de la transformation structurale
eschatologique du discours de l’université au discours de l’analyste (cf. fig.
21), puisque c’est ce qui devrait se produire dans la psychanalyse pour qu’elle
aboutisse à la fin.
Comme je l’ai déjà dit, le discours de l’université est notre mode
d’existence quotidien. Hegel l’appelle Entfremdung (aliénation) et
Heidegger Verfallenheit (déchéance, dévalement). Dans cette structure,
le signifiant maître S1, en obturant le trou apophatico-ontologique,
refoule le sujet $ pour s’y substituer (Urverdrängung). Alors le
sujet $ est poussé hors de sa propre place (la place de la vérité) dans
la place de la production qui est celle de l’ex-sistence, celle de ce qui ne
cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible) et celle de Verborgenheit
(cèlement). Le moi S2 s’identifie au signifiant maître S1
en tant que surmoi pour devenir das Man (le on). Mais maintenant, dans
la phase eschatologique de l’Histoire de l’être, l’obturation du trou ne
peut plus se maintenir stablement comme dans la phase métaphysique, de sorte
que le trou veut toujours s’ouvrir et surgir (aufgehen) malgré la
résistance et la défense que nous formons contre l’Aufgehen angoissant
du trou. Et quand le trou s’ouvre et surgit effectivement, ce n’est pas par la
voie régressive du discours de l’université au discours du maître, mais par la
voie progressive du discours de l’université au discours de l’analyste, que le
trou surgit bordé par le bord formé du sujet $. Pour ainsi dire, le trou
du sujet $ au moment archéologique du discours du maître était an
sich, tandis qu’après l’expérience dialectique de l’analyse, le trou du
sujet $ au moment eschatologique du discours de l’analyste est an und
für sich.
Dans la transformation structurale eschatologique, le signifiant maître S1
est forclos de la place de ce qui obture le trou (la place de la vérité) dans
la place de l’impossible (la place de la production). Si le S1
déifié dans la place de la vérité n’est que le Dieu symbolique et l’idole
métaphysique, c’est-à-dire le Dieu que Pascal appelle Dieu des philosophes et
des savants, alors le S1 forclos et recelé (geborgen) dans la
place de l’impossible (ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire) est le Dieu réel
et vivant dans son mystère. C’est ce Dieu que Pascal appelle Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob.
Et cette forclusion du S1 induit l’Aufgehen du trou du
sujet $ qui se lève (ἀνάστασις, résurrection) de la place de
l’impossible (la place de Verborgenheit) pour se révéler dans la place
du nécessaire (le bord du trou, la place d’Unverborgenheit). Si on entre
dans les détails, le sujet $ dans la place de la production du discours
de l’université est ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible). Mais
par la transformation eschatologique du discours de l’université au discours de
l’analyste, ce sujet $ cesse de ne pas s’écrire (le contingent) pour
devenir ce qui ne cesse pas de s’écrire (le nécessaire) dans le discours de
l’analyste.
L’Aufgehen eschatologique du trou du sujet $ n’est rien
d’autre que ce dont il s’agit dans la phénoménologie telle que Heidegger la
définit comme ἀποφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα (faire voir à partir de lui-même ce qui
se montre tel qu’il se montre à partir de lui-même). Et cet Aufgehen
eschatologique du trou du sujet $ n’est rien d’autre que l’apocalypse
(révélation) eschatologique chrétienne.
Ainsi, dans le discours de l’analyste qui est la topologie de séparation
(cf. fig. 21), au moment de l’Aufgehen du trou du sujet $, la
surface sphérique qui se compose du S2 (le moi) et du petit a
(l’autre) se sépare de la surface möbiusienne du S1 (le Dieu réel),
le bord de laquelle est fait du sujet $. Comme nous pouvons le voir dans
le schéma du discours de l’analyste, nous avons maintenant la structure où le
sujet $ qui est dans la place du nécessaire (ce qui ne cesse pas de
s’écrire) est le représentant du S1 (le Dieu réel) qui est dans la
place de l’impossible (ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire) : $/S1. C’est-à-dire, maintenant, le
sujet $ se débarrasse de la relation imaginaire du moi (S2)
et de l’autre (a) pour entrer dans le vrai rapport avec Dieu, pour être
le représentant de Dieu, et ce pour faire la volonté de Dieu. Dans la prière du
Pater noster, nous disons que « fiat voluntas tua sicut in caelo et in
terra », mais ce « fiat » ne se réalise que quand nous faisons
nous-même la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, c’est le
saint, ce saint dont Lacan parle dans la Télévision pour autant que
l’« être un saint » et l’« être un psychanalyste » sont
équivalents l’un à l’autre dans leur formalisation de $/S1.
D’ailleurs, à cet égard, nous pouvons aussi nous souvenir de ce que Lacan dit
dans la séance du 25 mai 1955 de son Séminaire II (1954-1955) Le moi dans la
théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, où il fait cette
remarque : « C’est précisément en cela que consiste la formation de
l’analyste : le moi de l’analyste en tant que tel doit être absent. (…)
C’est ça qu’il s’agit d’obtenir toujours du sujet en analyse. » Le sujet $
qui s’est débarrassé de son moi S2, c’est bien cela qui se lève dans
le discours de l’analyste. En parlant de façon heideggérienne, nous pouvons
dire qu’à ce moment-là, le Seyn s’approprie (aneignen, ereignen)
de notre Dasein pour que s’y produise (sich ereignen) l’Ereignis
eschatologique qui consiste dans l’Aufgehen du trou du Seyn
(le sujet $) et dans le recèlement (bergen) du Dieu réel S1.
C’est pour cela que le Seyn a besoin de notre Dasein.
Ainsi, à la fin de l’analyse, en nous libérant de la relation imaginaire du
moi et de l’autre, nous devenons le vrai représentant de Dieu pour faire Sa
volonté sur la terre, laquelle volonté pour le psychanalyste consiste à aider
tout sujet qui lui demande l’analyse à parvenir à la fin de son analyse où le
sujet deviendra lui-même un représentant de Dieu. Et c’est dans ce sens que
nous pourrions bien dire que la psychanalyse est une des voies de restauration
du rapport avec Dieu.
En effet, nous en avons un témoignage personnel de quelqu’un que vous
connaissez : c’est le Dr Gérard Haddad qui témoigne dans son livre Le
jour où Lacan m’a adopté (2002) de cet épisode dramatique de l’éveil de la
foi en lui, lui qui était un marxiste athée avant cela. Un jour, il a eu une
querelle violente avec son père « tyrannique » et
« capricieux » au sujet de la célébration de bar mitzva
de son fils, laquelle querelle a fini par sa déclaration contre son père de la
rupture de la relation filiale. Il en parle aussitôt à Lacan, lequel le
félicite en lui disant : « Vous avez eu parfaitement raison ».
Mais à peine il quitte le cabinet du psychanalyste, que « quelque chose
bascula, et je me trouvai envahi d’une décision » de faire la volonté de
Dieu, c’est-à-dire de célébrer lui-même la bar mitzva de son fils. Alors
il se demande : « Que s’était-il passé au tréfond de mon être en ces
quelques secondes ? Quelque chose comme le meurtre symbolique du père
imaginaire, animal et sur la dépouille encore chaude le surgissement immédiat
de l’instance de la Loi » qui lui transmet la volonté de Dieu. Le
lendemain, quand il parle au psychanalyste de sa décision, « à ma grande
surprise, entendant mes propos, Lacan manifesta une sorte d’enthousiasme »
en lui disant ces louanges : « C’est formidable ! » Et
« il me serra longuement la main pour souligner l’importance du
moment ».
Ce n’est pas à la fin de son analyse avec Lacan que cet épisode s’est
produit, mais à mi-chemin. Néanmoins, nous pouvons voir ce qui s’est passé à ce
moment-là : par la forclusion violente du signifiant maitre (le Nom-du-Père)
S1 de la place de la vérité, il est arrivé un moment de la
transformation eschatologique du discours de l’université au discours de
l’analyste, par où le sujet $ devient un réalisateur de la volonté de
Dieu S1 recelé dans la place de l’impossible. Ce que nous suggère
cet épisode est ceci : la transformation eschatologique peut arriver à
n’importe quel moment, soudain et inopinément, puisque le moment eschatologique
ne se situe pas sur l’axe du temps. Je vous en présente encore deux exemples
qui sont historiques : l’un est celui de René Descartes et l’autre celui
de Blaise Pascal, lequel j’ai déjà mentionné ici plusieurs fois. Bien qu’ils
soient, tous les deux, des hommes du XVIIème siècle, c’est-à-dire bien avant le
commencement de la phase eschatologique de l’Histoire de l’être, nous
pouvons trouver chez eux des témoignages de l’expérience du moment
eschatologique.
L’exemple de Descartes est son cogito ergo sum (cf. fig. 22). Dans
l’histoire de la philosophie, ordinairement on considère le cogito
cartésien comme une forme du sujet transcendantal, c’est-à-dire on ne peut plus
métaphysique. Mais Lacan nous en suggère une autre interprétation dans son
Séminaire XI. Dans le doute méthodique cartésien, le cogito n’est rien
d’autre que le dubito qui induit la forclusion de toutes les
présuppositions scolastiques, lesquelles sont le S1 dans le discours
de l’université. Alors se produit, au moment de l’ergo, la
transformation structurale, de sorte que surgit avec toute la certitude le sum
$ dans la place de l’autre du discours de l’analyste, c’est-à-dire la
place du nécessaire et le bord du trou. Mais, étant donné que la séparation (le
discours de l’analyste) va vite revenir à l’aliénation (le discours de
l’université) dans la pulsation temporelle, cette apparition du sujet $
n’est qu’évanouissante.
Fac-similé du mémorial de Pascal
Le deuxième exemple est l’expérience mystique fulgurante de Pascal qu’on
appelle la Nuit de feu (cf. fig. 23), de laquelle il nous laisse le
témoignage en nous disant d’abord « Feu » (d’où la Nuit de feu),
et puis ceci : « [ Je crois en ]
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non [ au Dieu ] des
philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix… »
Ainsi, il s’agit d’une expérience intense de la certitude, de la joie et de la
paix, laquelle vient de la forclusion du « Dieu des philosophes et des
savants » (qui n’est en fait qu’une idole scolastique : le S1
à la place de la vérité dans le discours de l’université) et de la communion
mystique avec le Dieu réel (le S1 à la place de la production dans
le discours de l’analyste). Si je parle en anticipation, cette expérience de la
certitude, de la joie et de la paix est celle de la jouissance sublimatoire
dont il s’agit dans la fin de l’analyse.
Je viens de vous présenter seulement quelques exemples de l’expérience du
moment eschatologique, mais, en fait, il y en a innombrablement dans
l’Histoire : au premier chef, il faut nommer Jésus Christ, le Fils de
Dieu, mort et ressuscité le troisième jour, et puis tous les prophètes dans
l’Ancien Testament et tous les saints et toutes les saintes dans l’histoire du
christianisme. Bien sûr, je ne peux pas y entrer ici. Mais, de toute façon,
nous pouvons voir que le moment eschatologique peut arriver à n’importe quel
moment et à n’importe qui selon la volonté de Dieu, malgré notre résistance
face à l’Aufgehen du trou du sujet $ qui nous provoque
ordinairement l’angoisse intense : les angoisse du néant, de la mort et du
péché.
§ 7. Au-delà de l’Aufgehen du trou : la
sublimation
Comme j’y ai déjà fait allusion, ce n’est pas l’Aufgehn angoissant
du trou comme tel qui constitue la fin de l’analyse, mais la jouissance de
sublimation.
Comme vous le savez, Lacan traite la sublimation thématiquement dans son
Séminaire VII (1959-1960) L’éthique de la psychanalyse, et ce dans un
rapport avec l’amour courtois pour autant que cette forme d’amour exclut a
priori la possibilité de la jouissance du rapport sexuel. Dans son Séminaire X
(1962-1963) L’angoisse, il définit, en se référant à la sublimation,
l’amour en disant que l’amour est la sublimation du désir, et en même temps il
nous présente cette thèse : seul l’amour-sublimation permet à la jouissance
de condescendre au désir. Et s’il revient à la sublimation de temps en temps
jusqu’au moment du Séminaire XVI (1968-1969) D’un Autre à l’autre, il
n’en parle plus à partir du Séminaire XVII (1969-1970) L’envers de la
psychanalyse. Est-ce que cela veut dire que la sublimation perd son poids
dans l’enseignement de Lacan des années 1970 ? Je ne le pense pas,
puisqu’il continue de parler de l’amour courtois qui est pour lui l’exemple
favori de la sublimation. À cet égard, nous pouvons nous souvenir de cette
remarque de Lacan dans la séance du 20 février 1973 de son Séminaire XX
(1972-1973) Encore : « L’amour courtois est la façon tout à
fait raffinée de suppléer à l’absence de rapport sexuel ». Donc nous
pouvons dire que Lacan continue de penser à la sublimation en tant que seul
l’amour-sublimation peut suppléer au trou du non-rapport sexuel. Alors nous
pouvons poser cette hypothèse : comment formaliser de façon topologique la
sublimation pour autant qu’elle est la suppléance au trou du non-rapport sexuel ? :
cette question est, si on ne peut pas dire le seul, mais au moins un des thèmes
majeurs du dernier enseignement de Lacan.
Or, au commencement de cet exposé, j’ai cité cette proposition : « Das Selbstbewußtsein erreicht
seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein » (la
conscience de soi n’atteint sa satisfaction que dans une autre conscience de
soi) que Hegel nous présente un peu avant la fin de la partie introductive
(c’est-à-dire un peu avant le commencement de la section sur la dialectique du
maître et de l’esclave) du chapitre sur le Selbstbewußtsein
de sa Phänomenologie des Geistes. Si Hegel définit le Selbstbewußtsein
comme Begierde (désir), c’est parce qu’il (Selbstbewußtsein) veut résoudre la division ou la différence d’avec
lui-même (cf. fig. 24) et restaurer l’unité avec lui-même.
Ce désir est le
ressort même du mouvement dialectique qui devrait aboutir, pour Hegel, au
savoir absolu où la division entre le savoir et la vérité est résolue. Mais
s’il dit dans cette proposition-là que le Selbstbewußtsein en tant que désir n’atteint la
satisfaction que dans l’Autre Selbstbewußtsein en tant qu’Autre désir, qu’est-ce que tout cela veut
dire, surtout dans la dimension de la philosophie hégélienne, laquelle n’est
rien d’autre que la théologie selon Hegel lui-même ? Cela voudrait dire
que la division du Selbstbewußtsein d’avec lui-même
n’est rien d’autre que la division entre l’homme et Dieu, et que cette
satisfaction finale serait la jouissance sublimatoire de la réconciliation, de
la communion et même de l’union mystique entre l’homme et Dieu, dans lesquelles
l’un et l’Autre se connaissent parfaitement. Alors le savoir absolu ne serait
rien d’autre que cette connaissance mutuelle parfaite de l’homme et de Dieu,
dans laquelle nous demeurons en Lui et Lui en nous (cf. 1 Jn 4,13).
Pour Lacan, telle est le modèle de la sublimation pour penser à la
sublimation dans la psychanalyse. Or, il est hors de doute qu’il a rencontré
pour la première fois cette proposition hégélienne comme telle énigmatique dans les cours qu’Alexandre Kojève faisait
sur la Phénoménologie de l’Esprit dans les années 1930, c’est-à-dire au
début de la période préparatoire de son enseignement. Et, comme nous allons le
voir ci-dessous, Lacan continue de penser à la sublimation jusqu’au tout
dernier moment de son enseignement. De là, je dirai ceci : tout
l’enseignement de Lacan est des commentaires sur cette proposition
hégélienne : « Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung
nur in einem anderen Selbstbewußtsein », puisque cette satisfaction finale
est la jouissance de sublimation qui conditionne la fin de l’analyse.
Alors, tout comme
le moment eschatologique peut arriver n’importe quand, la jouissance
sublimatoire aussi peut se produire à n’importe quel moment. Nous en avons vu
un exemple chez Pascal qui l’exprimait, sans utiliser ce mot-clef, comme la
joie du salut, lequel est joyeux parce que Dieu nous donnera, au-delà du néant
de la consummatio saeculi, le nouvel être (bien sûr non métaphysique) de
la nouvelle création, au-delà de la mort dans ce monde, la vie éternelle dans
Son royaume, et au-delà du péché condamné par la Loi, la rémission du péché par
Lui qui est tout miséricordieux. Tout comme cela, il doit y avoir, au-delà des
angoisses du néant, de la mort et du péché, la jouissance de sublimation dans
la psychanalyse aussi.
En effet, nous en avons un exemple, et cette fois-ci aussi celui de Gérard
Haddad qui nous raconte dans son livre Le jour où Lacan m’a adopté cet
épisode :
À la fin d’une séance particulièrement abrupte, j’éprouve
une angoisse infinie. Je m’apprête à endosser mon manteau quand partir ainsi
m’apparaît impossible, insupportable. Je décide, en une impulsion incontrôlée,
plutôt que de quitter le cabinet, de revenir dans la salle d’attente, me tenant
debout, comme menaçant. Lacan a déjà pris le patient suivant. Quelques minutes
plus tard, il se présente dans l’encadrement de l’autre porte, poursuivant la
folle noria de ses consultations. Il m’aperçoit. « Que voulez-vous ? »
me demande-t-il inquiet. « Vous parler ! » « Venez. Que se
passe-t-il ? » me demanda-t-il après que nous étions de nouveau dans son
bureau, tout en restant debout, près de la porte. Il semble en colère, excédé.
C’est alors que je prononce ces mots auxquels je n’ai pas réfléchi :
« Je me sens foutu ! » lui dis-je. « Vous ne vous sentez
pas foutu, vous êtes foutu. » Et il ajoute aussitôt :
« Je vous vois demain. » Aussi paradoxal que la chose puisse
paraître, ce « vous êtes foutu », c’est-à-dire, une fois encore,
castré, me soulagea. Je me surpris même à sourire.
Comme vous le remarquez, cette conversation instantanée où à ce « Je
me sens foutu ! » d’Haddad réplique Lacan en disant :
« Vous êtes foutu » ressemble à un mot d’esprit. Et, en fait,
elle est recueillie, sous une forme déformée, dans le livre Les Impromptus
de Lacan : 543 bons mots recueillis par Jean Allouch. Et il y a des gens
qui traitent le rapport du Witz à la sublimation, mais je n’y entrerai
pas. Ce que je voudrais vous faire remarquer ici, c’est ceci : Haddad,
étant tout au bord du trou apophatico-ontologique, était dans une dépression
angoissante assez grave pour se sentir « foutu ». Alors les mots
tranchants et impitoyables de Lacan, le poussant encore vers le trou, lui
provoquent soudain ce renversement où la souffrance et l’angoisse se
transforment dans une jouissance sublimatoire, aussi petite qu’elle soit,
puisqu’à ce moment-là, Haddad n’éclate pas de rire dans une exultation, mais il
sourit seulement. De toute façon, il se dit soulagé : soulagé du poids de
l’angoisse, étant poussé un petit peu au-delà du trou.
Moi aussi, je vous présenterai un exemple de mes expériences : un rêve
que j’ai eu il y a quelques années. Alors que je marche seul quelque part dans
une ville, il surgit soudain, à partir du sein de mon manteau, un bébé couvert
de sang. Surpris, j’essaie de le repousser pour le cacher là où il était avant
son surgissement, mais je n’y arrive pas. Angoissé, je me réveille. À ce
moment-là, j’ai un très fort sentiment de culpabilité, et je me demande si je
l’ai tué, et je continue de me demander ce que signifie ce rêve. Alors,
quelques semaines après, aussi soudain, cette interprétation me vient dans la
tête : ce bébé couvert de sang, je l’ai enfanté, non pas tué. Le mot
japonais que je traduis ici par le mot sein, signifie principalement les
parties de vêtements qui couvrent la poitrine, et avec ce mot on peut dire par
exemple « le sein d’Abraham » en japonais. Bien qu’il n’ait pas
lui-même le sens d’utérus, par l’association avec le mot français sein,
il peut signifier pour moi cet organe reproducteur aussi, lequel je ne possède
pas dans mon corps masculin. Donc, pour que j’enfante, le bébé doit surgir du sein
de mes vêtements. Alors j’ai cette certitude : moi, j’ai enfanté à la fois
moi-même et l’Enfant Jésus, puisque c’est lui qui fait mon être même. Et si je
dois naître de nouveau, c’est parce que Jésus nous dit : « à moins de
naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu » (Jn 3,03). Ainsi,
en moi, l’angoisse et le sentiment de culpabilité se transforment en jouissance
sublimatoire sous la forme de la joie de nouvelle naissance et de salut.
Alors, cette jouissance sublimatoire au-delà de l’Aufgehen
angoissant du trou, comment Lacan la formalise-t-il ? Comme je l’ai déjà
suggéré, dans le graphe du désir (cf. fig. 25), ce mouvement dialectique du
désir $ qui, en passant par le lieu du signifiant A et par la pulsion ($ ◊ D), arrive à
l’Autre désir S(Ⱥ), schématise le chemin de la sublimation.
Alors, comment ce mouvement est-il
schématisé dans les quatre discours ?
D’abord voyons le schéma de
l’aliénation (fig. 15) où le lieu de l’Autre en tant que lieu du signifiant est
le domaine coloré bleu, lequel correspond à la place de l’agent où se situe le
S2. Ce qui manque dans le lieu de l’Autre est l’Autre-de-l’Autre,
c’est-à-dire le signifiant maître S1 qui se situe à la place de la
vérité (jaune), c’est-à-dire à la place de ce qui obture le trou
apophatico-ontologique. Donc le manque dans l’Autre est ce trou même. Alors le S(Ⱥ), le signifiant du manque dans l’Autre, désigne
le bord du trou (vert). Dans ce schéma de l’aliénation, ce qui fait le bord du
trou est le petit a, lequel se situe à la place de l’autre dans les
quatre discours. Donc le mathème S(Ⱥ) désigne le
bord du trou dans le schéma de deux cercles et la place de l’autre dans les
quatre discours.
Ensuite voyons la transformation du discours de l’université (l’aliénation)
au discours de l’analyste (la séparation) (cf. fig. 21), dans laquelle le sujet
$, d’abord caché dans la place de la production (la place de
l’impossible : rouge), surgit, par cette transformation structurale, dans
la place de l’autre (la place du nécessaire : vert) qui correspond au
mathème S(Ⱥ).
Donc nous pouvons dire que le mouvement
du sujet $ qui aboutit au S(Ⱥ) dans le graphe du désir est schématisé,
dans les quatre discours, par ce mouvement du sujet $ qui se déplace de
la place de la production (rouge) dans la place de l’autre (vert) par la
transformation du discours de l’université au discours de l’analyste. Ce sujet $
dans le discours de l’analyste, qui est l’Urbegierde et qui est arrivé
dans la place du S(Ⱥ) qui est l’Autre désir, c’est la formalisation de la Befriedigung
du Selbstbewußtsein dans la communion avec
l’Autre Selbstbewußtsein. Et ce sujet $ qui est le désir sublimé
dans le discours de l’analyste, c’est ce que Lacan appelle désir de l’analyste.
Alors, nous pouvons dire que l’analyste fonctionne par son désir de l’analyste
comme la place du S(Ⱥ) qui va accueillir le sujet $ de l’analysant pour
qu’il atteigne la sublimation, lui aussi.
Mais, comme on le voit dans le schéma
de la séparation, le trou du sujet $ (plus précisément le trou bordé du $)
surgit là comme un simple trou ouvert, lequel nous angoisse comme le trou du
néant, de la mort et du péché. Alors comment formaliser la jouissance
sublimatoire en tant que suppléance au trou du non-rapport sexuel ?
Je pense que c’est pour répondre à cette question-là que Lacan déploie tous
ses efforts dans le Séminaire XXIV (1976-1977) L’insu que sait de
l’une-bévue s’aile à mourre et dans le Séminaire XXV (1977-1978) Le
moment de conclure. Nous pouvons lire ces deux Séminaires consécutifs comme
un seul, puisqu’il me semble que Lacan ne trouve ce qu’il cherche dans son
Séminaire XXIV que vers la fin de son Séminaire XXV. En effet, dans la séance
du 15 mars 1977, il déplore qu’il ne trouve pas ce qu’il cherche en disant
qu’il tourne en rond. Par contraste, dans les trois dernières séances du
Séminaire XXV (celles du 11 avril, du 18 avril et du 9 mai 1978), il trouve, me
semble-t-il, ce qu’il cherche, c’est-à-dire une formalisation topologique de la
jouissance sublimatoire en tant que suppléance au trou du non-rapport sexuel.
Alors, sous quelle forme ? Sous la forme de nœud de trèfle pour autant que
ce nœud s’obtient à partir du bord de la bande de Möbius à la torsion de trois
demi-tours.
D’ordinaire, quand on dit tout simplement bande de Möbius, il s’agit de la
surface unilatère qu’on obtient en unissant bord à bord les deux extrémités
d’une bande avec une torsion d’un demi-tour (BM1) (cf. fig. 26). Si on en
découpe le bord, alors on obtient ce que Lacan appelle huit intérieur
dans son Séminaire XI et qu’on appelle dans la théorie des nœuds nœud
trivial, c’est-à-dire, en anglais, unknot : ce qui ne fait pas
un nœud au sens ordinaire du terme.
Or, ce que Lacan nous présente dans le Séminaire XXV, ce n’est pas la BM1, mais
la bande de Möbius qu’on obtient avec une torsion de trois demi-tours (BM3)
(cf. fig. 27). Si on en découpe le bord, on obtient le nœud de trèfle.
Mais quelle est la signification psychanalytique de cette caractéristique
de la BM3 ? Lacan ne nous en dit rien. Alors il nous faut revenir à la
topologie du plan projectif (cf. fig. 11).
Puisque la BM3 est homéomorphe à la
BM1, on peut obtenir un plan projectif en identifiant le bord de la BM3 avec le
bord du trou de la sphère trouée ou du bord du disque (PP-BM3). Et supposons
que la Providence fait ceci : dès le départ, ce qui sert de modèle pour la
topologie apophatico-ontologique, c’est le PP-BM3, non pas le PP-BM1.
Maintenant, voyons la figure 28. La surface möbiusienne $/S1
qui se sépare de la surface sphérique a/S2 au moment de la
séparation est une BM3, non pas une BM1. Donc le sujet $ qui fait le
bord de la surface möbiusienne est un nœud de trèfle, non pas un simple bord du
trou. Et avec ce nœud de trèfle, Lacan formalise la suppléance au trou du
non-rapport sexuel.
Dans l’expérience psychanalytique, nous pouvons constater ce fait : au
moment de l’Aufgehen du trou du sujet $, l’analysant est dans
l’angoisse assez intense ; à ce moment-là, il faut que l’analyste le
soutienne avec son propre trou du $ ou du S(Ⱥ) et avec des interprétations adéquates ; alors
arrive le moment de la jouissance sublimatoire où il s’avère que le sujet $
qui a surgit ouvert n’est pas un simple trou, mais un nœud de trèfle.
Une patiente qui est catholique mais qui ne sait rien de la théologie ni de
la philosophie ni de la théorie psychanalytique, m’a dit un jour, dans une
séance au bout de sept ans ou huit ans de l’analyse, qu’elle sent près
d’elle-même une présence de quelque chose comme la mort ou le néant, et donc
qu’elle a peur, mais qu’en même temps elle est dans la paix et très heureuse.
Le moment de la jouissance sublimatoire peut être comme cela.
§ 8. Le phallus et le trou du non-rapport sexuel
Depuis que Lacan l’a énoncée pour la première fois dans son Séminaire XVI
(1968-1969) D’un Autre à l’autre, la formule « il n’y a pas de
rapport sexuel » a fait couler beaucoup d’encre, mais je ne sais pas s’il
y a quelqu’un qui l’a mise dans le contexte de la critique lacanienne du
phallocentrisme freudien, lequel est exprimé partout dans ses textes, mais
conceptualisé surtout dans les complexes d’Œdipe et de castration et dans sa
théorie du développement libidinal.
Le phallocentrisme consiste dans cette supposition qu’il y ait le phallus
symbolique ou le signifiant phallique Φ qui puisse obturer le trou apophatico-ontologique.
Alors cette supposition donne la signification du manque phallique ( − φ ), c’est-à-dire de la castration (cf. fig. 29) au trou
qui est proprement le trou du néant, de la mort et du péché, comme nous
l’indiquent les expériences cliniques de la psychanalyse.
Néanmoins cette
supposition phallique s’atteste bien avant l’ἰδέα platonicienne
sous la forme de Dionysies, c’est-à-dire orgies dionysiaques, où se déroule la
procession qu’on appelle τὰ φαλληφόρια ou τὰ φαλλαγώγια et où, comme ces noms
l’indiquent, on transporte un énorme phallus de bois (cf. fig. 30) en tant que
symbole de la fertilité, de la vitalité et de la jouissance sexuelle.
Fig. 30
Ce cratère avec la figure d'une φαλλοφόρος est estimé être produit vers 470 av J-C
Ainsi,
dans le domaine de culte ou de religion, il y avait un S1 obturateur
du trou sous la forme du phallus Φ qui était déjà adoré bien avant la période
présocratique, et qui donc pourrait être un des plus anciens S1 ou
même le plus ancien S1 dans l’Histoire. Et ce phallocentrisme dure
jusqu’à Freud, et au-delà, jusqu’à nos jours.
Pour vous expliquer la formule « il n’y a pas de rapport
sexuel », je voudrais d’abord attirer votre attention à cette expression
de Lacan dans son Rapport de Rome : la « mythologie de la maturation
instinctuelle ».
Il s’agit d’une critique contre la théorie freudienne du développement
libidinal, où on suppose ceci : au commencement, il y a des pulsions
partielles prégénitales ; ensuite, elles sont intégrées sous le primat du
phallus comme la pulsion sexuelle : alors on est dans la phase
phallique ; et à ce moment-là, le complexe d’Œdipe est à l’apogée de ses
activités. Mais, étant donné que les organes génitaux de l’enfant sont
prématurés, le processus du développement entre dans la période de latence
jusqu’au commencement de la puberté, dans laquelle le développement libidinal
atteint au stade final de maturation que Freud appelle Genitalorganisation (organisation
génitale), et alors la pulsion sexuelle peut servir à sa propre finalité,
c’est-à-dire à la procréation. Les objets de la critique de Lacan sont ces deux
concepts équivalents l’un à l’autre : le primat du phallus et l’organisation
génitale. La maturation de la pulsion sexuelle sous le primat du phallus est
mythologique, puisque cette supposition que la finalité de la pulsion sexuelle consiste
dans la procréation n’est qu’une téléologie métaphysique. Le phallus qui
réaliserait l’organisation génitale est impossible (ce qui ne cesse pas de ne
pas s’écrire) : voilà ce que veut dire la formule « il n’y a pas de
rapport sexuel ». Lacan aurait pu dire que la Genitalorganisation
est impossible, mais il préfère un sensationnalisme pour bien impressionner son
auditoire.
Si vous relisez les cas de Freud, vous pouvez remarquer quelles gaffes il
commet à cause de sa conviction du phallocentrisme et du complexe d’Œdipe, la
plus éclatante desquelles se trouve dans le cas de Dora. Si elle interrompt
l’analyse au bout d’à peu près onze semaines, c’est parce que la supposition
phallocentrique de Freud la dégoûte. Dans le cas du petit Hans, les
interprétations franchement œdipiennes que le père donne à son fils nous font
rire. Vous pouvez aussi remarquer comment le phallocentrisme empêche de
s’apercevoir dans ses cas de l’importance de l’Aufgehen du trou
apophatico-ontologique. Dans le cas de Dora, il s’ouvre sous la forme de
l’incendie qui va la dévorer dans son premier rêve et sous la forme de la mort
de son père dans son second rêve. Dans les cas du petit Hans et de l’Homme aux
loups, il s’ouvre sous la forme de la gueule du cheval ou du loup. D’ailleurs
Freud néglige l’importance de l’accident où un grand cheval qui tire un lourd
chariot se renverse devant les yeux de Hans qui pense que le cheval va mourir.
Pour nous, il est tout à fait clair que c’est cette rencontre brusque et
traumatisante du trou de la mort, non pas le complexe d’Œdipe, qui déclenche la
phobie chez Hans. Dans le cas de l’Homme aux loups, le trou va aussi s’ouvrir,
dans son épisode paranoïaque, sous la forme de pores multiples ouverts sur son
nez. Dans le cas de l’Homme aux rats, c’est d’abord dans son fantasme le trou de
l’anus et celui de la gueule du rat qui dévore les viscères de l’intérieur, et
puis le trou de la Schuld (dette et culpabilité) à l’endroit des filles
pauvres, lequel trou, impossible à combler, il s’efforce néanmoins d’obturer dans
ses comportements obsessionnels. Si Lacan faisait le contrôle du jeune
psychanalyste Freud, il lui dirait : « laissez de côté le complexe
d’Œdipe, et vous allez mieux voir ». En fait, Lacan dit dans son Séminaire
XVII (1969-1970) L’envers de la psychanalyse que le complexe d’Œdipe est
« strictement inutilisable » dans la pratique et qu’il « ne sert
à rien aux psychanalystes ».
Enfin, voyons comment le phallocentrisme empêche Freud de penser
adéquatement au problème de la fin de l’analyse dans son article Die
endliche und die unendliche Analyse (1937) où il dit dans le dernier
paragraphe ceci :
On a souvent
l’impression, avec le Penisneid (le désir de pénis chez les femmes) et le
männlicher Protest (la protestation virile, c’est-à-dire l’angoisse de
castration ou Penisangst qui est le terme que Freud utilise comme le
pendant masculin au Penisneid féminin), d’avoir traversé toute la
stratification psychologique jusqu’au »gewachsener Fels« (soubassement
immense de roc) et d’être ainsi arrivé à la fin de son action.
C’est-à-dire, pour Freud, l’expérience psychanalytique est vouée à aboutir à
l’impasse conditionnée par la nécessité du phallus Φ qui puisse obturer le
trou apophatico-ontologique pour empêcher le surgissement de l’angoisse. Il lui
est impensable d’aller au-delà du trou, en endurant pendant quelque temps
l’angoisse devant le trou ouvert, pour atteindre à la fin authentique de
l’analyse. Telle est la limite de Freud qui ne peut pas se débarrasser de son
phallocentrisme. Certes, Lacan se dit toujours freudien, non pas lacanien, pour
déclarer que c’est lui qui est l’héritier véritable du père fondateur, mais
cela ne doit pas empêcher qu’on s’aperçoive que son enseignement comporte des
critiques importantes contre la théorie freudienne, et ce pour qu’il aille
au-delà de l’impasse phallique pour penser plus adéquatement à la fin de
l’analyse et à la formation de l’analyste.
Les notes :
La traduction anglaise de
cet article a été lue dans la téléconférence de l’Association slovène de la
psychanalyse lacanienne le 18 janvier 2025. Je remercie Mme Nina Krajnik, la
présidente de ladite Association, de m’avoir invité à y parler. Puisque dans un
document écrit avec un logiciel de traitement de texte, comme l’est ce texte
que je suis en train d’écrire, on ne peut pas barrer un mot d’une croix, je me
contente de biffer ces mots d’une ligne : Sein, Seyn ou être.
L’orthographe Seyn
était utilisée jusqu’au XIXème siècle. Dans ses textes publiés de son vivant,
Heidegger écrivait en principe Sein, mais dans ceux qu’il n’avait pas
l’intention de publier de son vivant, il écrivait Seyn à partir de 1931
pour le différencier, me semble-t-il, du Sein de la tradition
ontologique.
Le terme mathème,
introduit dans l’enseignement de Lacan au cours de son Séminaire de 1971-72 …ou
pire, vient du μάθημα (ce qui s’apprend,
science) et du suffixe -ème (élément) comme le terme linguistique phonème
vient du φώνημα et du -ème. Lacan désigne par là
des symboles formels tels que S1, S2, $ et a
qu’il place dans ses schémas mathématico-topologiques tels que le schéma L, le
graphe du désir et les quatre discours.
Cf. Heidegger, M. :
Nietzsche. Gesamtausgabe (GA) 6.
Lacan, J. (1953) :
Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Écrits,
p.289.
Le terme « archéologique » veut dire ici qu’il
s’agit du commencement (ἀρχή) que Heidegger appelle anderer Anfang,
c’est-à-dire l’autre commencement que celui de la métaphysique ou celui des
pensées dans la Grèce antique en général. Et comme on le verra, l’archéologie
va de pair avec l’eschatologie.
C’est par ces deux mots « ἐν
ἀρχῇ » que commencent le Livre de la Genèse dans la Septante et l’Évangile
selon Jean.
Heidegger, M. : Nietzsche.
GA 6.1, p.431.
Le terme allemand Neuzeit
comprend l’époques moderne et l’époque contemporaine.
La traduction du mot Endzeit
serait « époque finale », c’est-à-dire
« époque eschatologique ». Cf. Heidegger, M. :
Nietzsche. GA 6.2, pp.35-40.
Masson, J.M. (1984) : The Assault on Truth.
Haddad, G. (1981) : Lacan
et le judaïsme.
Lacan,
J. (1958) : D’une question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose. Écrits, p.563. Lacan, J. (1974) : Télévision.
Autres écrits, pp.519-520.
Heidegger, M.
(1957) : Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik. GA 11, p.77.
J’interprète ce
terme néosémique Austrag comme un nom heideggérien du trou
apophatico-ontologique dans le contexte de la question de la différence
ontologique.
Heidegger, M. (1949)
: Einleitung zu: »Was ist Metaphysik?« GA 9, p.376.
Cf. Heidegger, M. :
Seminar in Le Thor 1969. GA 15, p.344.
Lacan,
J. (1956) : Le séminaire sur « La Lettre volée ». Écrits,
p.11.
Le cas est relaté
par Freud dans le chapitre IV La déformation du rêve de L’interprétation
du rêve. Dans son écrit La direction de la cure, Lacan fait une
petite plaisanterie en appelant cette patiente « spirituelle
bouchère » puisqu’elle est l’épouse d’un boucher et que Freud dit qu’elle
est witzig (cf. Écrits, p.625).
Maintenant, quand
on parle des nœuds que Lacan appelle nœuds borroméens généralisés dans son
Séminaire XXVI (1978-1979) La topologie et le temps, on dit dans les
mathématiques les entrelacs brunniens (Brunnsche Verschlingungen, Brunnian
links) d’après le nom de Hermann Brunn (1862-1939), le mathématicien
allemand qui les décrit dans son article Über Verkettung (1892). Alors
le nœud borroméen est l’entrelacs brunnien le plus simple qui se compose de
trois éléments.
Lacan, J. (1960) :
Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien.
Écrits, p.818.
La bar-mitzvah
est une cérémonie pour les jeunes garçons juifs qui atteignent treize ans,
laquelle représente le moment où un jeune homme devient responsable pour
observer les commandements religieux et engager sa vie comme membre adulte de
la communauté juive. Le pendant féminin en est la bat-mitzvah qui se
célèbre à l’âge de douze ans.
Lacan,
J. (1953) : Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse.
Écrits, p.263.





















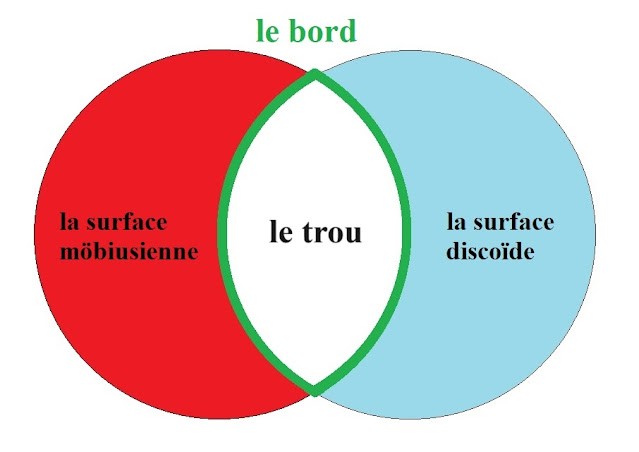









.jpg)









